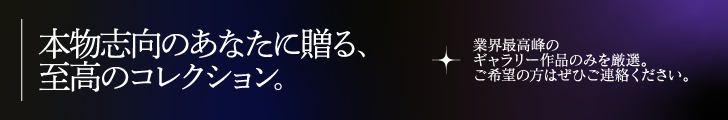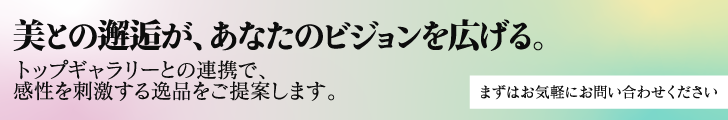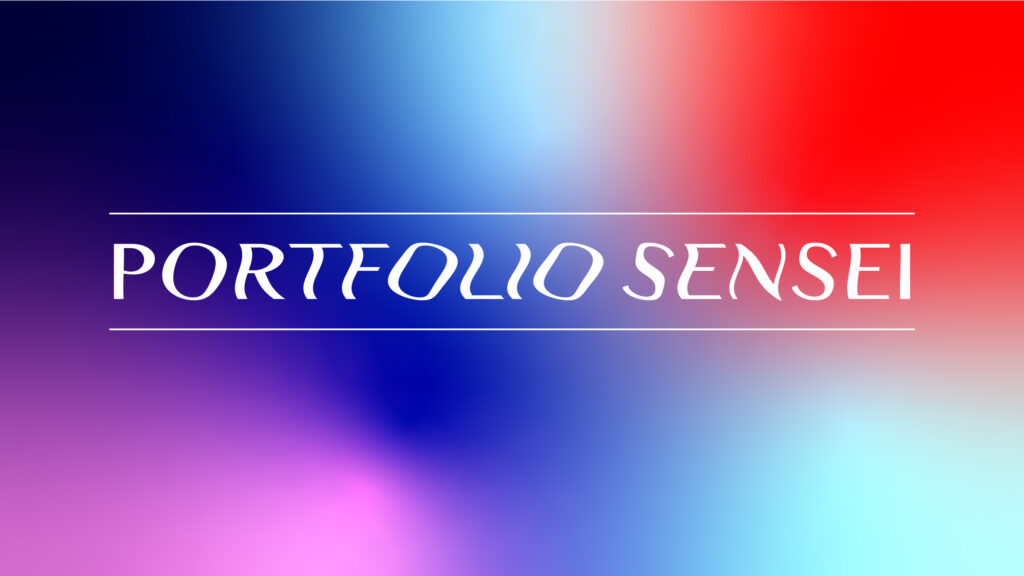こんにちは、ユアムーン編集部です。
皆さんは「マリー・ローランサン」という人物をご存知でしょうか。
マリーはバイセクシュアルの画家で、作品は動物、女性を描いたものが多くパステル調の色彩が特徴的です。生涯を通じて女性の独立や愛情、創造性などをテーマに作品を制作し、男性芸術家が多くを占めた20世紀初頭の美術運動に大きな影響を与えています。
また長野にはマリーの生誕100周年である1983年に、マリー・ローランサンに特化した「マリー・ローランサン美術館」が開館し、2019年までコレクションの公開がされていました。(現在は閉館しています)
今回はそんなマリー・ローランサンの人生と作品についてご紹介していきます。
コンテンツ
Toggleマリー・ローランサンってどんな人?

photographed by Carl Van Vechten, 1949
| 本名 | マリー・ローランサン(Marie Laurencin) |
| 生年月日 | 1883年10月31日 |
| 出身 | フランス パリ |
| 学歴 | アカデミー・アンベール |
| 分野/芸術動向 | 絵画、版画、彫刻 / 表現主義 |
人生と作品
生まれと環境
マリー・ローランサンは1883年10月31日にフランスのパリで非嫡出子として生まれます。
大人になるまでは母のポーリーヌ・ローランサンとともに一緒に暮らしており、政治家である父親は時折二人の元に現れるくらいでマリーからはあまり良い印象を持たれていませんでした。
幼少期はヨーロッパの王妃の肖像画を集めたり修道院に行ったりしていて、様々な本を読み絵を描くのが好きでしたが、学校の成績は最下位だったようです。
美術教育
10代後半を「悲しく、醜く、希望がなかった」と語るマリーは学業不振の反省から自画像を描き始め、18歳の頃、磁器生産で有名なセーヴルにあるセーヴル美術学校で磁器の絵付けを学び、1903年にパリに戻りアカデミー・アンベールで美術の教育を受けます。
アカデミー・アンベールではデッサン、絵画、版画などを学び、ここで後の前衛芸術の中心となる「ジョルジュ・ブラック」や「フランシス・ピカビア」らと出会いました。
1900年代の自画像
マリーはその生涯を通じて自画像を描き続けており、被写体として自分自身を使ったのは、女性の自立と自己形成への関心からと言われています。
関連記事:
ナタリー・バーネイのサロンに参加
同時期にマリーは、フランスの作家でありレズビアンを公言していたナタリー・バーネイが主催するサロンに参加するようになります。
そのサロンには主にレズビアンやバイセクシュアルの女性が交流し、女性の欲望や創作活動について語り合っていました。
生涯を通して「女性」という一貫したテーマで絵画を描き続けたのは、このサロンでの交流の影響が少なからずあるのではないでしょうか。
展覧会デビューとアポリネールとの出会い
1907年、24歳のマリーはクロヴィス・サゴ画廊で開催されたアンデパンダン展にて展覧会デビューを果たし、その時にすでに知り合いであったパブロ・ピカソから詩人の「ギヨーム・アポリネール」を紹介されます。
そしてマリーとアポリネールは6年の間交際を続けます。
キュビスムは1911年のアンデパンダン展で広く知られるようになった事や、ピカソら前衛画家たちとの交流が深かったことからキュビストたちはマリーを自分の仲間だと主張したようですが、彼女自身はそのように作品を特徴づけられることを好ましく思っていませんでした。
アポリネールとの交際をしている間、アポリネールはマリーについて頻繁に執筆し、彼女を「キュビスムの聖母」などとよび、キュビスムとの関係がより強いものになります。
マリーは交際中もその後も自分の作品をキュビスムになぞらえることに抵抗をしていて、その代わりに彼女はアポリネールなど近代詩人の夢を彷彿させる雰囲気や、オーギュスト・ルノワールなどの印象派の柔らかい色彩を参考にしていたようです。
ギヨーム・アポリネールGuillaume Apollinaire (1916) ギヨーム・アポリネール(Guillaume Apollinaire、1880年8月26日 – 1918年11月9日)は、フランスの詩人、小説家、美術・文芸評論家。代表作に「ミラボー橋」を含む自由律の詩集『アルコール(英語版)』、ピカソ、ブラック、ローランサンらの「新しい画家たち」を絶賛した評論『キュビスムの画家たち(英語版)』、シュルレアリスムの演劇『ティレジアスの乳房』(フランシス・プーランクのオペラの原作)と小説『虐殺された詩人』、ジャンフランコ・ミンゴッツィ(フランス語版)監督によって映画化された性愛小説『若きドン・ジュアンの冒険』などがある。処女詩集『動物詩集』の副題にある「オルフェ」からオルフィスムの概念が生まれたほか、シュルレアリスム、カリグラムもアポリネールの造語である。
Apollinaire and His Friends (1909)

この作品は友人とマリーに囲まれるアポリネールが描かれています。
アポリネールは中央に座り、左側にはガートルード・スタイン、フェルナンド・オリヴィエ、そして見知らぬ女性が、右側にはパブロ・ピカソ、マルグリット・ジロ、モーリス・クレムニッツが並んでおり、マリーは青いドレスを着て地面に座っています。
マリーはガートルード・スタインが同じタイトルの小さな絵画を購入したことを受けて、そのオマージュとアポリネールへのプレゼントとしてこの絵画を制作しました。
アポリネールはこの絵をアパートのベッドの上に飾り、生涯をここで過ごしたそうです。
第一次世界大戦とダダ運動への参加
1913年にマリーの母親が亡くなると、彼女はアポリネールと別れ、アカデミー・アンベール時代の同級生だったファン・ヴァエチェンと1914年に結婚します。
しかし、マリーはアポリネールが1918年に38歳で亡くなるまで親密な関係を築いていました。
第一次世界大戦が勃発すると、ドイツ人の夫に対するフランスの反ドイツ感情を避けるべくスペインに移ります。ここでマリーはダダ運動に加わり、フランシス・ピカビアとともにダダイスムの情報雑誌「391」の編集に携わります。
そして1919年、マリーはファン・ヴァエチェンとの離婚を申請します。
戦後の心境やスタイルの変化
マリーの性格やスタイルは戦後、閉鎖的になり一般的な芸術スタイルへの試みは辞め、現在広く知られているパステル画の女性や犬の肖像画を制作するようになります。
この時代はココ・シャネルの肖像画を制作したり、ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」やキャサリン・マンスフィールドの「ガーデンパーティー」の挿絵を手がけたり、舞台装置や衣装デザインを手がけたりと制作のジャンルは多岐に渡ります。
1920年代の作品
Wikiart, https://www.wikiart.org/
Wikiart, https://www.wikiart.org/
Wikiart, https://www.wikiart.org/
Wikiart, https://www.wikiart.org/
シャネルが肖像画を依頼したのはバレエダンサーの「セルゲイ・ディアギレフ」の衣装を二人がデザインしていた頃でした。
肖像画が完成しシャネルに見せるとマリーの描くシャネルが全く自分に似ていない事から、シャネルはこの肖像画を却下します。
マリーはこの指摘に否定はしませんでしたが、身体的な類似性は重要ではないと主張しました。
彼女の発言はしばしば軽率であり、全ての女性の顔は飼い猫の顔を基にしていると主張したり、極度の近眼でメガネをかけていない自分の見たものを描いているだけなどとも主張することもあったようです。
この肖像画がシャネルに却下されたにも関わらず、このマリーのアプローチは成功を収め、第二次世界大戦までこのスタイルで肖像画の依頼を受け、制作していたようです。
晩年
晩年、マリーはうつ病や様々な体調不良に悩まされます。
マリーは1925年から同居していたメイドのスザンヌ・モローを法的に養子にして遺産の受取人としました。マリーとモローが恋愛関係にあったかは不明ですが、親密であったことは確かなようです。
そしてマリーは1956年に心臓発作で亡くなります。埋葬時には彼女の希望通りに白いドレスを着てアポリネールのラブレターとバラを手にしていたようです。
まとめ
いかがでしたか?
今回は女性や動物のパステル画を描き、女性の儚さを表現し続けた画家、マリー・ローランサンについてご紹介させていただきました。
マリーや、マリーと交流のあったブラック、ピカソなどキュビスムの作品は10月3日(火)より国立西洋美術館で開催される「キュビスム展―美の革命」で実際に作品を見ることができますので興味がある方はご覧になってはいかがでしょうか?
↓↓無料招待券のプレゼントも行っておりますので、ぜひご確認ください!↓↓