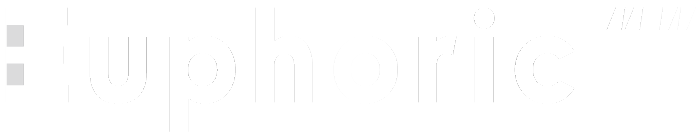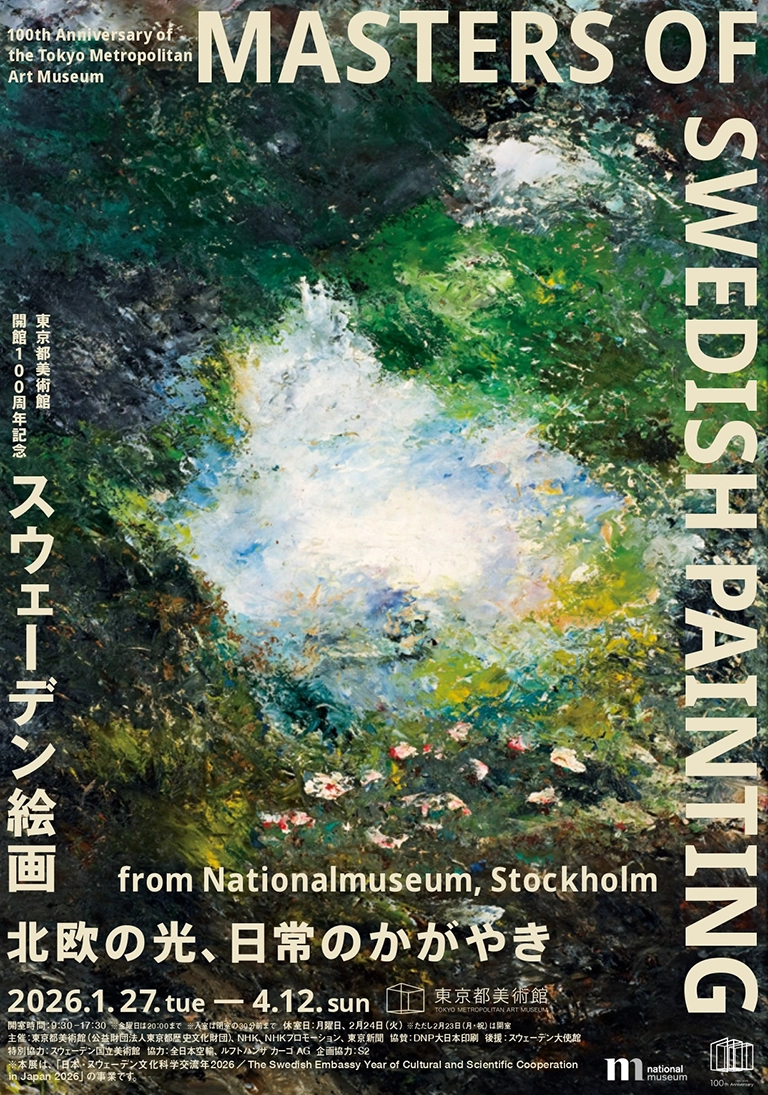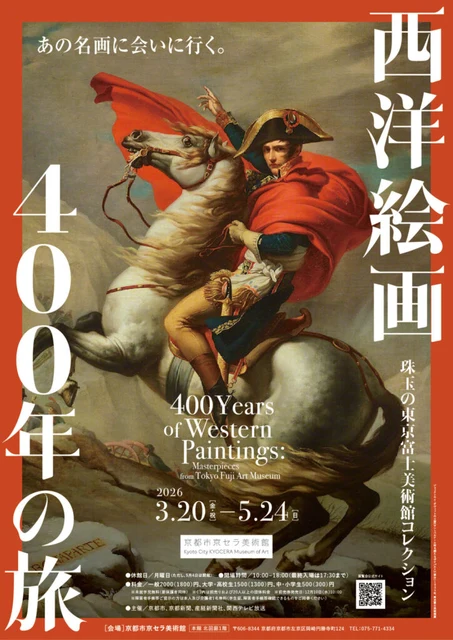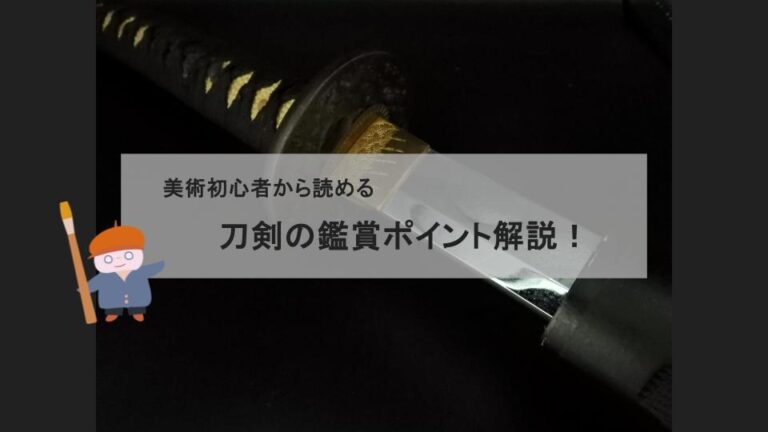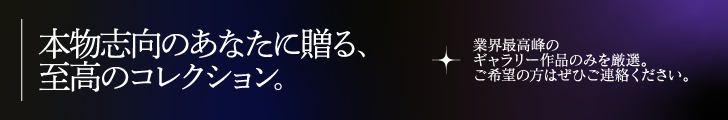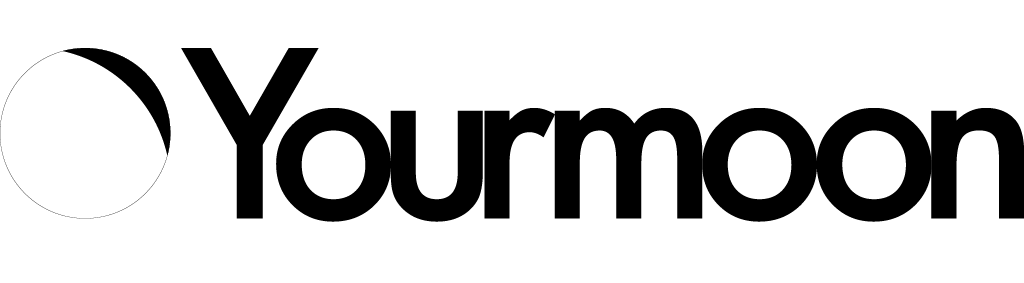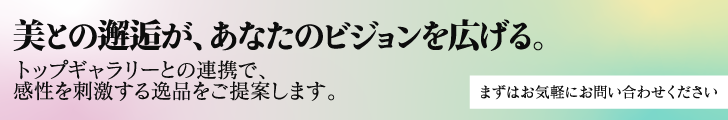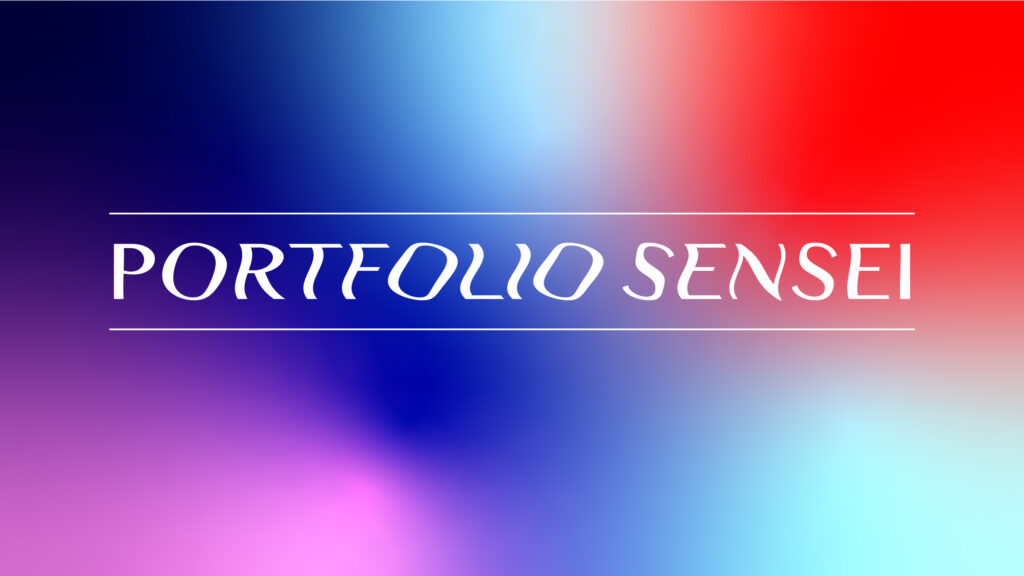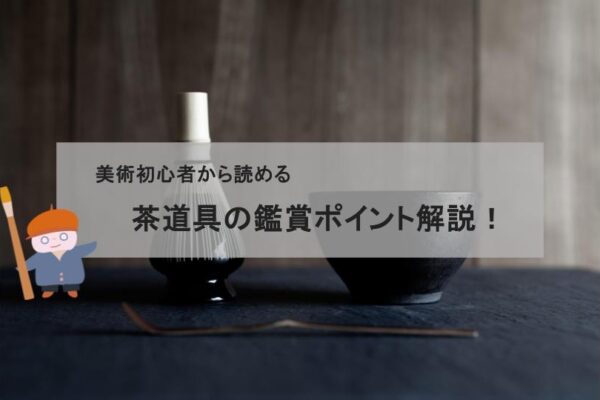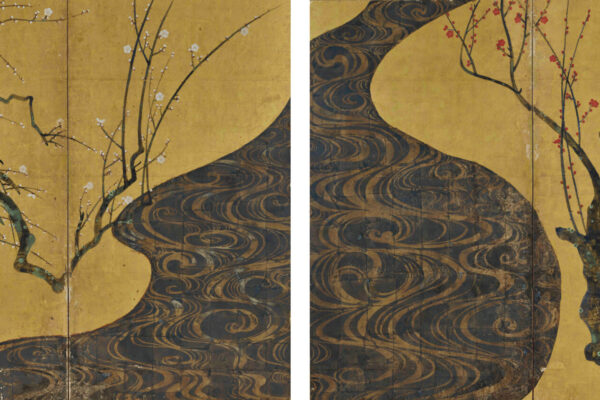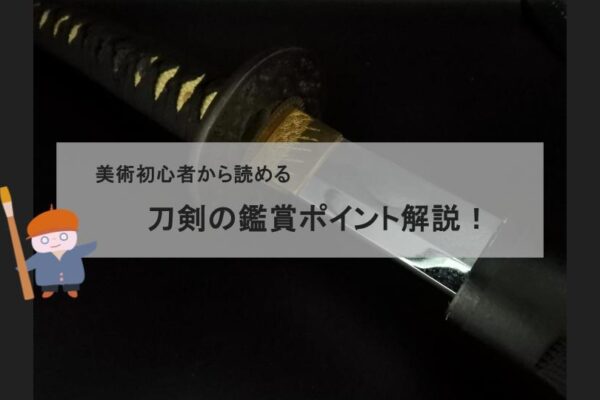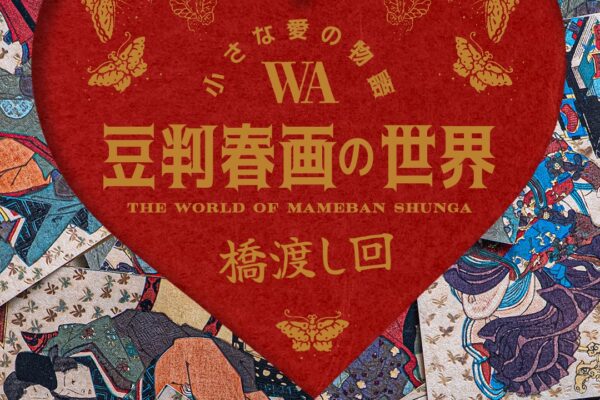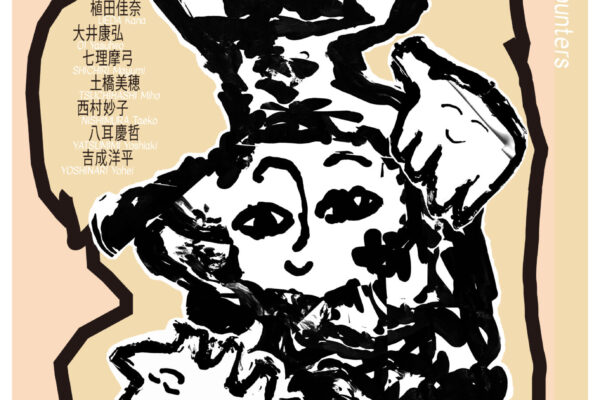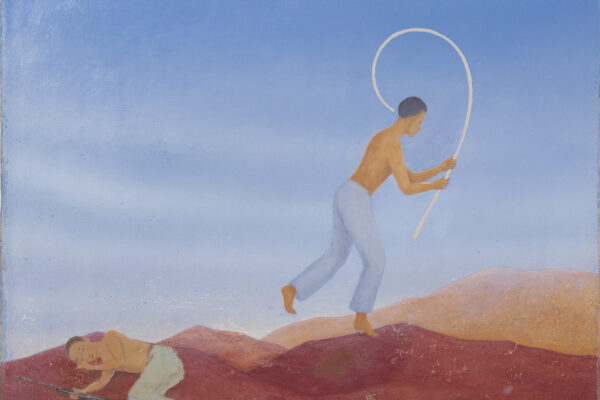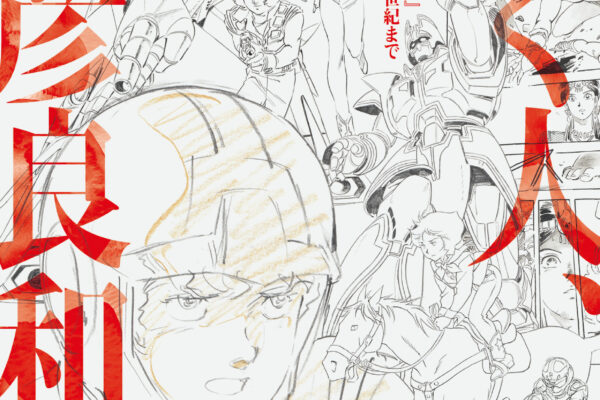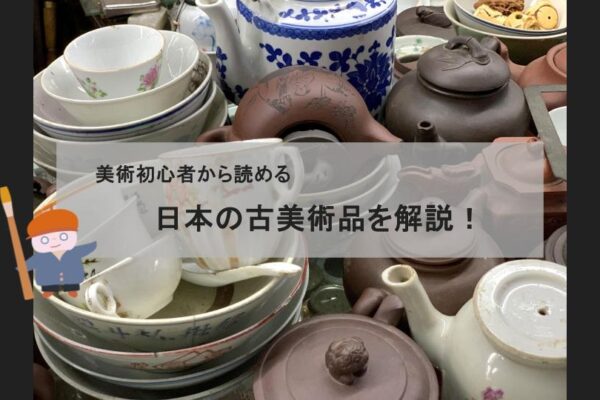こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。
皆さんは内藤廣という人物をご存知ですか?
『海の博物館』などの代表作で知られる現代建築家で、日本建築学会賞や文部科学大臣賞などの功績を持つ人物です。
現代建築界隈の第一線で活躍しながら、芸術教育や育成にも寄与している教育者でもあります。
2001年から2011年まで東京大学の教授を務め、退官された後も東京大学名誉教授として名前を残しています。
2023年には多摩美術大学の学長に就任されました。
本記事ではそんな内藤廣の人生と作品についてご紹介します。
コンテンツ
Toggle内藤廣について
基本情報
| 本名 | 内藤廣(Naito Hiroshi) |
| 生年月日 | 1950年8月26日- |
| 出身/国籍 | 日本 神奈川県横浜市 |
| 学歴 | 早稲田大学理工学部建築学科 |
| 分野 | 建築 |
| 傾向 | 現代建築 |
| 師事した/影響を受けた人物 | 吉阪隆正、フェルナンド・イゲーラス |
人生と作品
生い立ち
1950年8月26日、神奈川県横浜市に生まれました。
早稲田大学理工学部の建築学科で建築を学びます。恩師である吉阪隆正に師事しつつ、学生ながら建築専門誌『新建築』の評論欄で執筆活動を行っていました。
大学院修了後、スペインに渡り建築家フェルナンド・イゲーラスのもとで経験を積みます。帰国後、吉阪隆正の勧めで菊竹清訓建築設計事務所に入所します。
1981年に独立し、株式会社内藤廣建築設計事務所を設立しました。
『海の博物館』(1992)
代表作であり出世作でもある『海の博物館』(1992)は三重県鳥羽市にある博物館です。
1971年に鳥羽一丁目に設立され、1985年には所蔵品の「伊勢湾・志摩半島・熊野灘の漁撈用具」6879点が国の重要文化財に指定されているなど文化的に貴重な施設です。
現在の浦村町への移転に際し、内藤廣建築設計事務所が手がけることになりました。
移転前は塩害に悩まされてたことから、外装には極力金属を用いず、すべての屋根を日本瓦葺としました。
当時バブル経済時代にあったこともあり、低コストで竣工できたことも注目されました。
古今東西、建築は予算と切っても切れない関係にあるものです。
最近では新国立競技場や大阪万博など大規模な建築が話題になりましたが、その中でも予算や環境配慮といった観点は特に注目されています。
その点で、日本の伝統建築にみられる木造は金属・コンクリートに比べて耐用年数に課題があるものの、コストを低く抑えることができ、国産木材を利用できる、二次利用が可能などのメリットがあります。
このため、課題をうまく解決しながら木造のメリットを活かす建築がサステナビリティが求められる現代建築の流行となっています。
『海の博物館』の重要文化財収蔵庫も計画当初は木造を考えていましたが、木造では文化庁からの補助金が交付されないためプレキャストコンクリート造に変更しました。
しかし後から設立された展示場と体験学習棟は木造が取り入れられており、重要文化財収蔵庫と共通のアーチ状の梁で大空間を作っています。
30年以上前の作品でありながら木造とコンクリート造の良いところ取りをして現代建築と同じ課題に応えている、先見性のある建築と言えるかもしれません。
1992年に日本文化デザイン賞を受賞、公共建築百選に選ばれます。
翌年の1993年には日本建築学会賞作品賞、芸術選奨文部大臣新人賞、吉田五十八賞を受賞。
さらに近年、2021年に日本建築家協会JIA25年賞を受賞しました。
現代建築にも通じる内藤廣の先見性がわかる評価の高さではないでしょうか。
『とらや工房』(2007)
内藤廣は『とらや御殿場店』(2006)、『とらや東京ミッドタウン店』(2007)、『虎屋京都店』(2009)など老舗和菓子店とらやの店舗や改装をたびたび手がけています。
私たちがよく見る「とらや」のイメージは、内藤廣のデザインから影響を受けている部分が大きいかもしれません。
その中でも『とらや工房』は自然公園の中にある文化施設として独特な雰囲気のある建物です。
『とらや工房』のある御殿場東山ミュージアムパークは元首相の岸信介旧別邸があった場所で、御殿場市に返還されたあと、土地を活かす文化施設として利用するという目的で現在整備が進んでいる施設です。
工房は梅林や竹林、池などを取り囲むように弧を描き、敷地内には自然の風景を楽しむためのあずまやも用意されています。
とらやは御殿場市に工場を持ち、提供される煎茶には、御殿場東山ミュージアムパークの敷地に隣接する茶畑で採れる茶葉が用いられています。
さきほどサステナブルな建築の一環として国産木材を使って木造建築を作るインセンティブがあると解説しましたが、その根幹は「地産地消」という考え方があります。
『とらや工房』は地元の茶畑と連動してお茶が提供されること、自然の風景を楽しむためのあずまやを用意するという点で、地産地消の考え方を強くコンセプトに置いているように感じます。
『東京メトロ銀座線 渋谷駅』(2020)
増改築が度々話題になる渋谷駅ですが、2020年に明治通り上に移設された東京メトロ銀座線も内藤寛が手がけています。
コンセプトは「フューチャーシティ」で、改札からホームにかけて「アーチ」が用いられているのが特徴です。
渋谷ヒカリエに接続する改札口は開放的な直線アーチで、高架下にマッチしたコンクリート造で作られています。
公共交通機関に関わる建築は工期の間も利用を停止するわけにもいかないため、できるだけ短い工期で、利用制限や騒音をできるだけ抑える必要があります。
『東京メトロ銀座線 渋谷駅』もホームの新設にあたり、下にあるバスロータリーや明治通りへの影響を最小限にしなければなりませんでした。
特に、工事に際してクレーンや足場を組むスペースを十分に確保することが難しいという大きな課題をクリアする必要がありました。
そこで採用されたのがM字の鉄骨アーチによる「スライド工法」です。
「スライド工法」とは鉄骨などの搬入のために必要なクレーンや足場を組むスペースが確保できない場合、クレーン作業ができる場所であらかじめ鉄骨を組み立て、設置場所へスライドさせるという方法です。
今回使用した鉄骨アーチはスライドレールが左右の設置面に二つあれば十分で、電車の運行に大きな影響を与えることなく鉄骨を組み立てることができました。
全長110mに渡りM字型の鉄骨アーチが並ぶ開放的な駅舎が完成しました。
まとめ
いかがだったでしょうか。
内藤廣の代表的な建築作品を三つご紹介しました。
経済や環境など身近な事情が明らかになっているのが現代建築の面白いところではないかと思います。
どちらも時代によって大きく変わるものです。多くの資源と予算を割く建築物だからこそ、その時代の潮流に振り回されてしまう側面があります。
そんな中で、類い稀ない先見性で建築の価値を見極めているのは驚くべきことではないでしょうか。
これから先、どのような作品が世に送り出され、残っていくのかを楽しみに見守っていきましょう。
おすすめ書籍
内藤廣をもっと知りたい方にはこちらの書籍がおすすめです!
「内藤 廣の建築 1992-2004 素形から素景へ1」
「内藤 廣の建築 2005-2013 素形から素景へ2」
内藤廣は著作が多く、一人称視点での建築思考について知ることができます。その中でも「内藤廣の建築」全二冊は自分の半生を彩る作品と、取り巻かれてきた時代について詳しく書かれています。