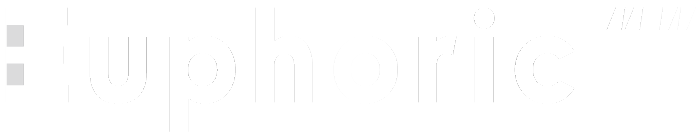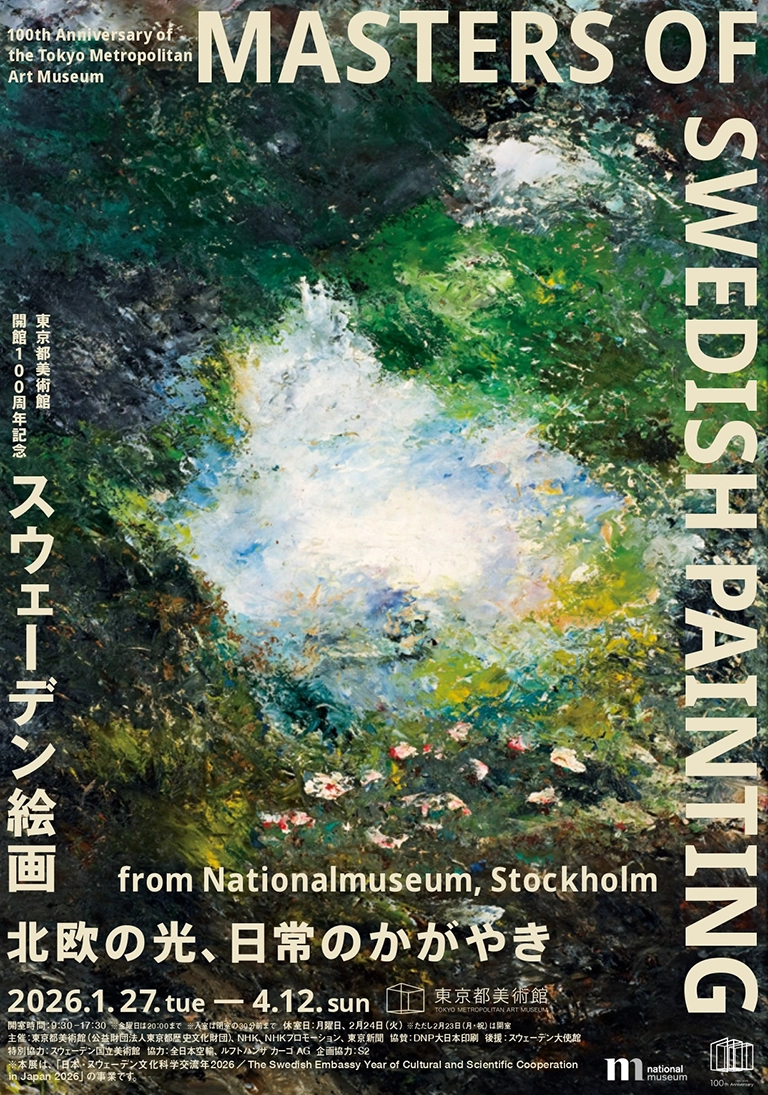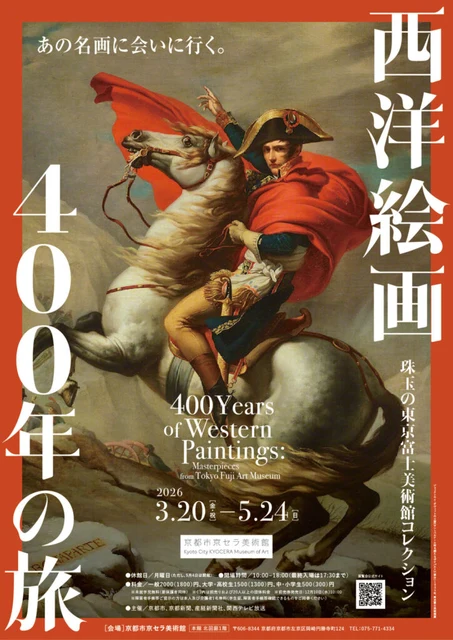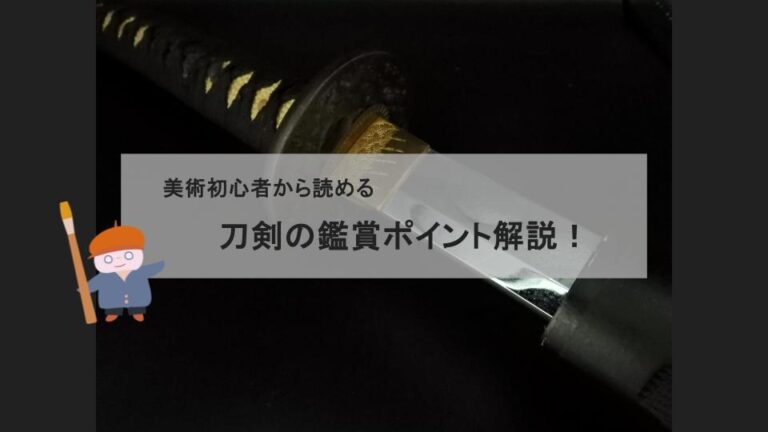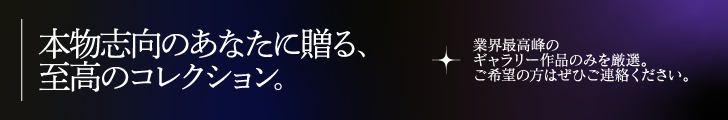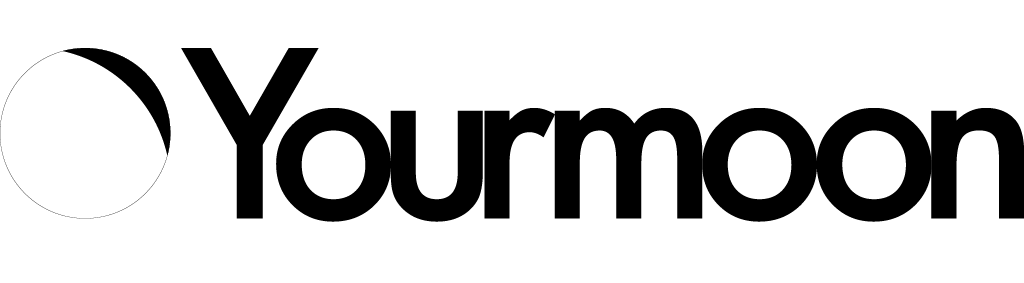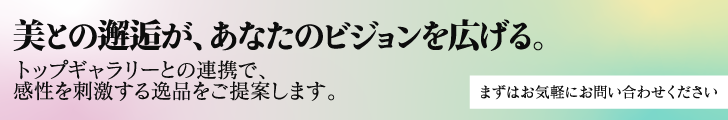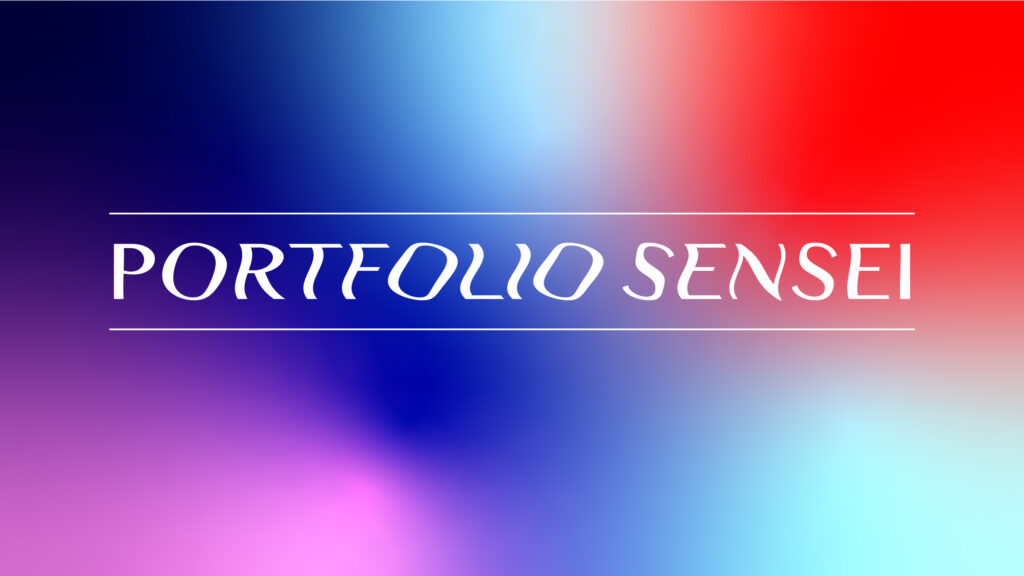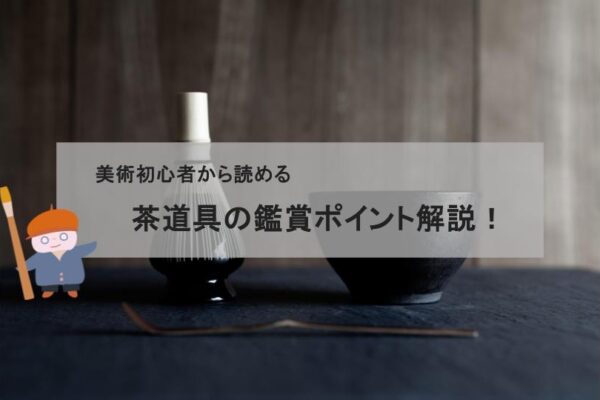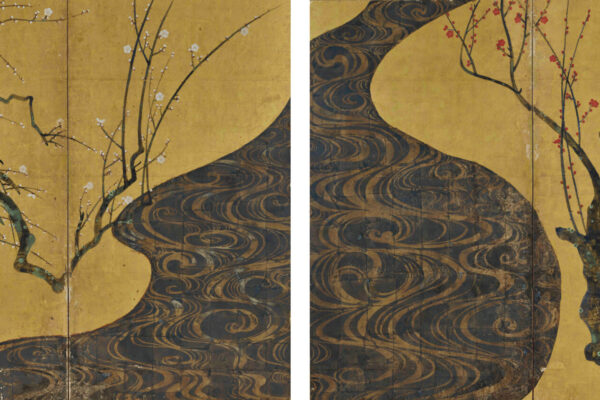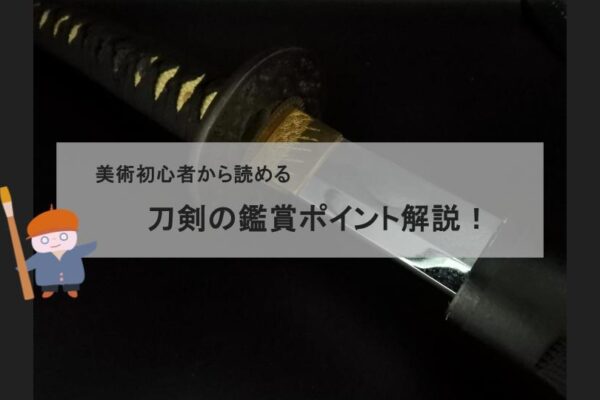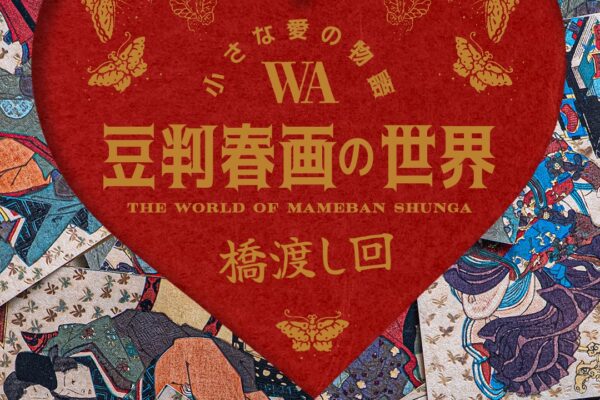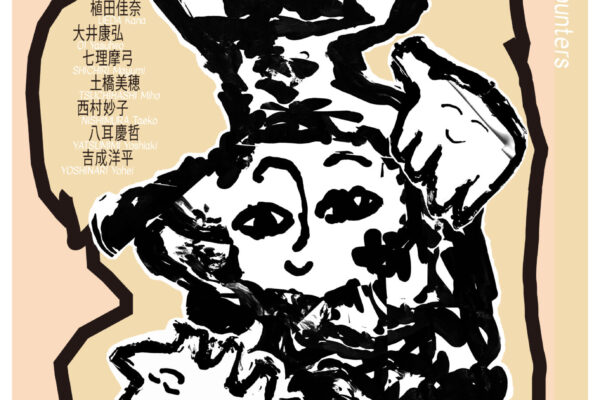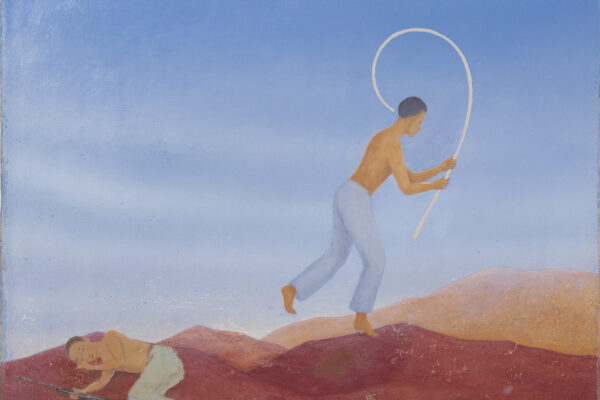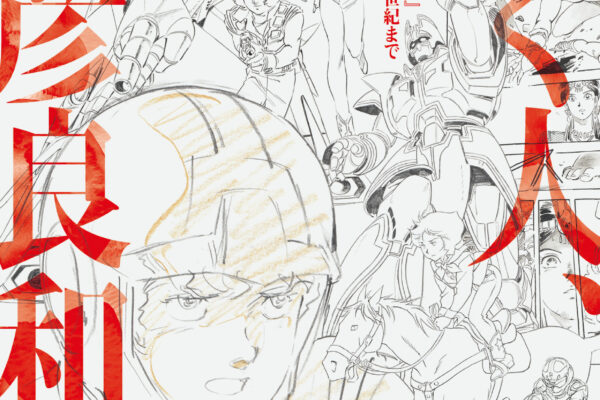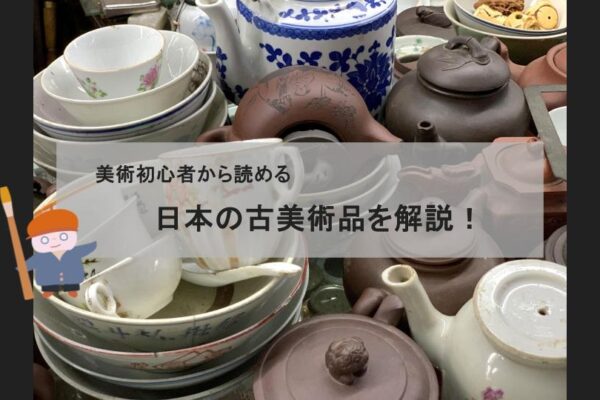こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。
皆さんは歌川広景という人物をご存知ですか?
ご存じない方も多いのではないでしょうか。歌川広重の門下でありながらあまり知名度のない彼ですが、詳しいプロフィールや生涯については不明な部分が多く、作品も約2年8ヶ月の制作期間で70点弱を残したのみです。
いわば知る人ぞ知る作家なのですが、実は歌川広重の門下であるという数少ないプロフィールとは打って変わって、滑稽でユーモラスな浮世絵を描いています。
本記事ではそんな歌川広景の人生と作品についてご紹介します。
コンテンツ
Toggle歌川広景って?
基本情報
| 本名 | 不詳(画号に歌川広景、別号に一葉斎がある) |
| 生年月日 | 出没年不詳 |
| 国籍/出身 | 日本(出身地不詳) |
| 学歴 | – |
| 分野 | 浮世絵 |
| 傾向 | 大版錦絵 |
| 師事した人物/影響を受けた人物 | 歌川広重、葛飾北斎など |
経歴と作品
まるでミステリー!?歌川広景の謎
『青物魚軍勢大合戦之図』(安政6年10月)
「藤岡屋日記」に記録されている当時の時勢を反映した作品。二つの軍勢を海の幸と山の幸で描き分けるというユーモラスさが魅力的です。
安政六年といえば「安政の大獄」で弾圧が行われた年でもあり、将軍継嗣問題を取り巻く一橋派と南紀派を描いているとも、前年に猛威を振るったコレラを踏まえて病気に罹りやすい海産物と罹りにくい野菜を描いているとも言われています。
歌川広景についての文献は非常に希少で、生年月日、家族、出身地といった個人情報は現在に至るまで謎のままです。
さらに、実は歌川広重の門下であるという根拠も希薄なものなのです。
昭和六年に出版された井上和雄による『浮世絵師伝』にある「【画系】初代広重門人」「歌川を称す」という記述を頼りに推察したものです。
現在確認されている作品はいずれも大判錦絵で、版本、摺物、肉筆浮世絵といったジャンルの作品は確認されていません。
広景の代表的な作品が『江戸名所道化尽』という全五十作のシリーズです。江戸の名所五十箇所を縦三十六センチ×横二十四センチの大版で描いた作品群ですが、確認できている制作年からするとこのシリーズがデビュー作ということになります。
デビュー作でいきなり大版の連作を手掛けるというのは不自然なことなので、これ以前から絵師としての仕事をしていたのだろうと推察することはできますが、肝心の作品が発見されていません。
また、歌川広景の素性についての一説として明治3年(1870年)から同7年(1874年)に活動した昇斎一景と同一人物とする説もあります。
彼は広景と同じく生没年や詳しい素性がわかっておらず、活動時間も短いという共通点があります。
昇斎一景の作品の中に文明開花を迎えた東京の名所を描いた「東京名所三十六戯撰」という作品群があります。
これは東京の名所とひとびとの滑稽な様子を描いた作品群という点で広景の「江戸名所道化尽」と一致しています。
これらの共通点から一景の「東京名所三十六戯撰」は広景の「江戸名所道化尽」を明治時代に置き換えた作風で、同一人物でもおかしくはありませんが、これを裏付ける資料はありません。
ただ、山々亭有人(明治時代に活躍したジャーナリスト)の記述によると、昇斎一景は円山応挙の画風を慕って京都を訪れたが、しばらく筆を断ち、再び東京に戻ってきて景色を描いたとあります。
また、江戸時代の事件や噂を記録した「藤岡屋日記」には歌川広景が横浜の外国人に絵を贈ったことに腹を立てた皇国有志連(おそらく尊王攘夷派のグループ)にお尋ね者扱いされていることが記録されています。
これらの記録を繋ぎ合わせると、歌川広景は江戸で絵師として活躍していたがお尋ね者となり、京都に身を隠し、再び東京に戻って新しい画号で活動を始めたというストーリーが見えてきます。
しかしこのストーリーを根拠づける文献や作品は発見されていません。
まるでミステリーのような来歴と噂の付き纏うアーティストですが、不可解さも歌川広景の魅力のひとつなのかもしれません。
笑いのお手本!?「御茶の水の釣人」
『江戸名所道化尽 四「御茶の水の釣人」』(安政六年正月)

お茶の水を流れる神田川で釣りをする人と、網で魚採りをする子供たち。うっかり釣り針は子供の髪の毛に引っかかってしまいます。
まだ悲劇に気づいていないもう一人の子供。目線を上げた時、どんな表情をするのか、広景タッチで考えてみるのも良いかもしれません。
古典的な笑いにクスッときてしまいますが、実は広景のオリジナルというわけではなく、葛飾北斎作『北斎漫画 十二編「釣の名人」』からそっくりそのまま引用した構図になっています。
北斎漫画というシリーズと、「釣の名人」というタイトルから、オリジナルの時点でギャグとして描かれていることがわかります。
また、構図は歌川広重作『東都名所 御茶ノ水之図』からの引用とされます。
ほとんどの要素がこの二作に拠るものですが、富士山を描き加えているのは葛飾北斎の『富嶽三十六景』を意識したものか、あるいはパロディ元を示すためのリスペクトなのかもしれません。
まるでコント!?「湯嶋天神の台」
『江戸名所道化尽 九「湯嶋天神の台」』(安政六年五月)

蕎麦の出前でも頼まれたのでしょうか、二人の男が蕎麦を運んでいると一人が野良犬に足を噛まれてしまいます。そんな時、運悪く武士が歩いてきました。思わず手を離してしまった蕎麦は宙を待って武士の頭に…。
誰の目にもそんなあらすじを思い描くような、明快な場面を描いたのがこの作品です。笑う蕎麦売りは、犬に噛まれた同僚にも蕎麦を引っ被った武士にも構わず指をさし、頭を抱えて笑っています。
「こりゃ傑作だ!」というセリフが聞こえてくるようではありませんか。
武士も予期せぬトラブルに巻き込まれたことに怒りが湧き上がっているようですが、コミカルなへの字口と歌舞伎の見得切りのようなおかしみのあるポーズが笑いを誘います。
そんなポップな作品ですが構図は美術的に興味深く、歌川広重が多用したように手前の物を拡大して遠近感を表現するという技法がこの作品を始め多くの絵で取り入れています。
プロ芸人のアドリブ!「外神田佐久間町」
『江戸名所道化尽 十「外神田佐久間町」』(安政六年六月)

凧が空を舞うお正月の風景。江戸の町には烏帽子を身につけた太夫と太鼓を鳴らす才蔵という二人組の芸者が家庭を回って祝言を述べ、身振り手振りで芸を行う万歳と呼ばれる行商人がいました。そんな万歳の二人が町を歩いていると、太夫の烏帽子が凧の紐に攫われてしまいます。
そんなハプニングに慌てることなく、とっさにおどけて舞を踊ってみせる太夫と、よしきたとばかりに太鼓に手を伸ばす才蔵。機転の効いた芸に通行人の女性や子供は大笑い。そんなほんわかするような日常を描いた作品です。
場所は武家屋敷の正門で、浮世絵に描かれることが少ない風景ゆえに武家の暮らしを知るうえでも重要な作品と言えます。
武士もしてやられたり!「下谷御成道」
『江戸名所道化尽 十一「下谷御成道」』(安政六年六月)

稽古帰りであろう武士に、子供が水鉄砲を食らわせるという様子を描いた作品。
今でいう風刺画というか、ブラックジョークのような不謹慎な笑いの雰囲気がある絵です。
子供が持っているのは竜吐水という子供のおもちゃで、火事の消火に使う道具を小型化したものです。
堂々、子供と武士は向かい合っている構図ですから、うっかりの事故という場面には見えません。
子供の笑顔を見れば「してやったり」という悪戯心が見てとれます。
水鉄砲を喰らった武士も驚き顔にも笑顔にも見える絶妙な笑顔。子供をからかっていたのか、遊んであげようとしたのでしょうか。
母親であろう女性は詫びようと駆け寄っていますが、こちらも引き攣ったような笑顔に見えないこともありません。果たして許してもらえたのでしょうか?
三者三様の笑顔でここまでストーリーが浮かび上がる広景の絵からは、その観察眼の鋭さとユーモア、なによりその表現を可能にする画力が見てとれます。
河童と喧嘩は江戸の華?「数寄屋かし」
『江戸名所道化尽 二十四「数寄屋かし」』(安政六年八月)

商人たちが喧嘩をしているようです。投げ飛ばされた様子の男が屋台に突っ込み、売り物が散らばってしまいます。駆け寄る仲間や様子を見にきた見物人が描かれる中、川から河童がやってきて、商品の瓜をしめしめと奪っていきます。
サラッと描かれた河童のインパクトについ笑ってしまう一作です。
とはいえ、舞台は江戸末期。少なくとも現代よりは妖怪の存在が信じられていたでしょうし、絵の題材としても多く描かれていました。
それでも混乱に乗じて盗みを働く河童の姿はどこか愛らしくシュールに見えます。
悲痛な顔をする商人に対して、駆け寄る仲間は何やら嬉しそうな表情。「あーあー、何やってんだい」と乱痴気騒ぎを楽しんでいるようにも、河童と目配せをしているようにも見えます。
もしかしたらこの喧嘩は仲間と河童が仕組んだものなのかもしれません。
本当にあった!ことわざ「芝飯倉通り」
『江戸名所道化尽 二十七「芝飯倉通り」』(安政六年九月)

「とんびに油揚げをさらわれる」ということわざがありますが、まさにその一瞬を捉えたような作品。
作品とことわざの成立のどちらが先かは分かりませんが、実際にこのような風景が見られたから生まれた言葉であることは間違い無いでしょう。
舞台は江戸湾からほど近い芝飯倉通りで、我々にもとんびがやってきそうな気配を感じます。
右の男性は顔に油揚げが乗ってしまっている上に、驚くあまり下駄の鼻緒が切れてしまっています。
左の男性は右の男性の挙動に慌てふためいているようにも、油揚げを取り返さんとしているようにも見えます。
また、当時の店の様子が伺える看板や陳列された鮭や蛸といったディテールも見所です。
鰻で賑わう江戸の町「両国米沢町」
『江戸名所道化尽 三十「両国米沢町」』(安政六年九月)

江戸でも有名な繁華街である米沢町には、江戸前名物・鰻の蒲焼を振る舞う蒲焼屋がいたるところにありました。
そんな蒲焼屋で、生きた鰻を店から逃してしまったようです。
勢い余って転びそうになる店主、(当時の文化的に)はしたないほど足を上げてびっくりする町娘、「そっちに行ったよ!」と言わんばかりに指を指す女性。
通行人はその様子を微笑ましく見守っています。
さらに左端には、二匹目のドジョウならぬ二匹目のウナギが脱走を試みています。
武士のおちゃめな一面「虎の御門外の景」
『江戸名所道化尽 三十四「虎の御門外の景」』(安政六年七月)

武士とそのお付きの頭上から、紐の切れた凧が落ちてきた瞬間を切り取った作品。なんといっても中央の従者の破顔ぶりが見事です。凧に引っ張られてか驚きのあまりか、はたまたその両方でしょうか、なんとも記憶に残る表情では無いでしょうか。
左の武士は驚くばかりでなく「曲者か!」と言わんばかりに刀を抜きかかっています。顔もまるで敵将や魔物を目の当たりにしているかのような見事な見得切りですが、相手はたかが凧。
そんな武士たちの混乱ぶりに、遠くに見える通行人は目もくれません。
そんな一枚の絵に閉じ込められた緩急が、武士の頭でっかちな立場を表現しているかのようです。
葛飾北斎ギャグ風パロディ「深川万年はし」
『江戸名所道化尽 三十九「深川万年はし」』(万延元年二月)

小名木川と隅田川の合流点に差し掛かる万年橋。その近くで漁をする海の男たち。漁師が力いっぱい網を引っ張ると、勢い余って網が切れて川にドボン…。
往年のコントを思わせるような状況設定に思わず吹き出してしまう一作です。
しかも網には大小数匹の魚しか掛かっておらず、漁師たちにとっては散々な結果であることが伺えます。
網越しに描かれた幻想的な富士山が漁師たちの哀愁を増します。
そんな芸術的とすら思える構図ですが、こちらも広景のオリジナルではなく、多くの要素を葛飾北斎作『富嶽百景 三篇「網裏の不二」』に拠っています。
もちろん葛飾北斎のものではきちんと漁師が網を引っ張っている様子を描いています。
「御茶の水の釣人」も同様に葛飾北斎からの引用でしたが、そこに川に落ちるハプニング、散々な釣果、驚き笑う乗員といった要素を描き加えることであらゆる要素が意味を変わる、見事なパロディといえるでしょう。
これが文明開花?「赤坂の景」
『江戸名所道化尽 四十五「赤坂の景」』(万延元年二月)

今でいう美容室や散髪屋にあたる髪結床では、町人が立ち寄っておしゃべりをする寄り合いのような場所でした。
そんな髪結床で、ハプニングが起きたようです。
うっかり髷を剃り上げてしまった店主。「やってくれたな」と不満げな客に苦笑いをしながら手を挙げてなだめています。
客が持っている器は切った髪が地面に散らばらないようにするものですが、そんな間もなくいきなり髷を落とされてしまったようです。
おしゃべりにきていたであろう他の客も大笑い。視線や手の形から、奥の男性は店主の失態を、手前の男性は客の無様な姿を笑っているように描き分けられているように見えます。
また、店内には落語や義太夫の宣伝チラシが描かれており、当時の店の様子を細かく知ることができる貴重な一作です。
まとめ
いかがだったでしょうか。
とってもヘン!な浮世絵師だったのではないでしょうか。
謎の来歴、名人絵師との関係性、ユーモラスな浮世絵…どれをとっても異質なアーティストだったのではないでしょうか。
鳥獣戯画や北斎漫画に端を発する戯画(面白おかしい様子を描いた大衆向けの絵画)が広まって間もなく、広景のようにほとんど戯画だけを残した作家がいたことは驚きです。
今でいうとギャグ専門の漫画家といった風でしょうか。
惜しむらくは、彼がどのような意図やインスピレーションで作品を描いたのかを知る手がかりが非常に少ないということです。
研究が進み歌川広景についての謎が明らかになることを願うばかりです。
おすすめ書籍
歌川広景をもっと知りたい方にはこちらの書籍がおすすめです!
『ヘンな浮世絵 歌川広景のお笑い江戸名所』
歌川広景の描いた「江戸名所道化尽」全五十作が収録された貴重な一冊。解説も読みやすく、希少な広景のプロフィールや研究者による考察も載せられています。わかりやすいユーモアの多い広景の作品ですが、とはいえ江戸〜明治の文化や時代背景の知識を要する部分も多いので、もう一笑いしたい方にお勧めです。