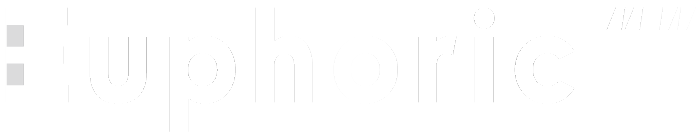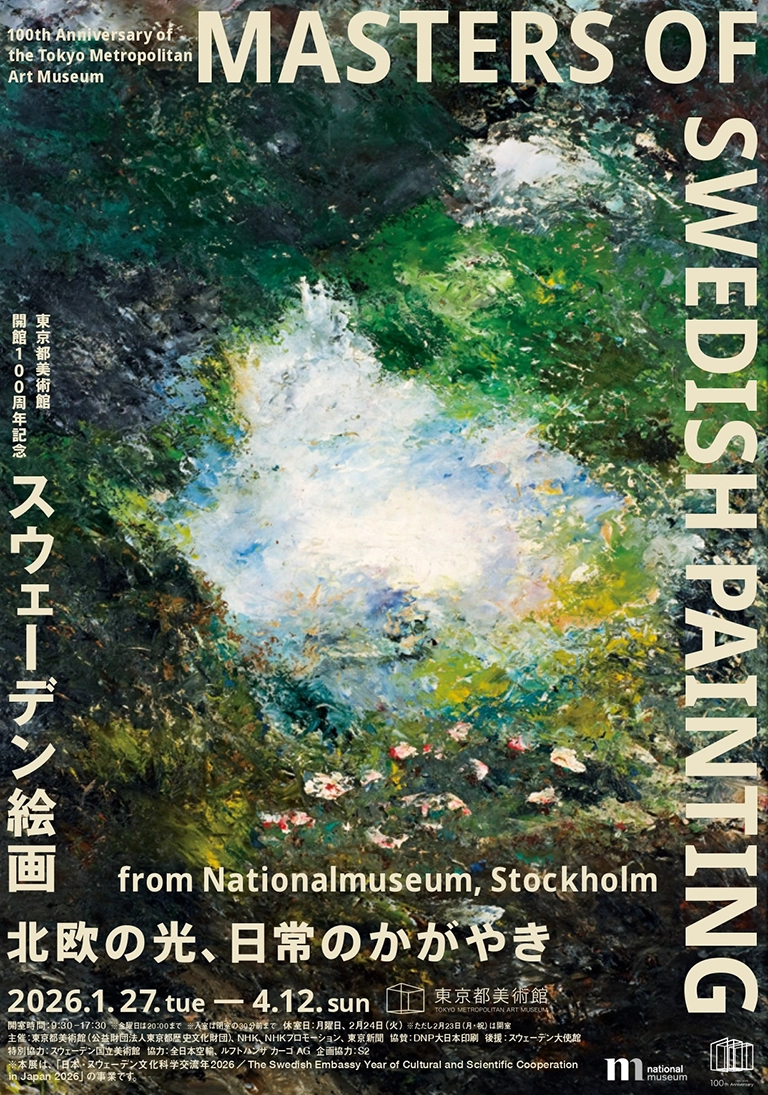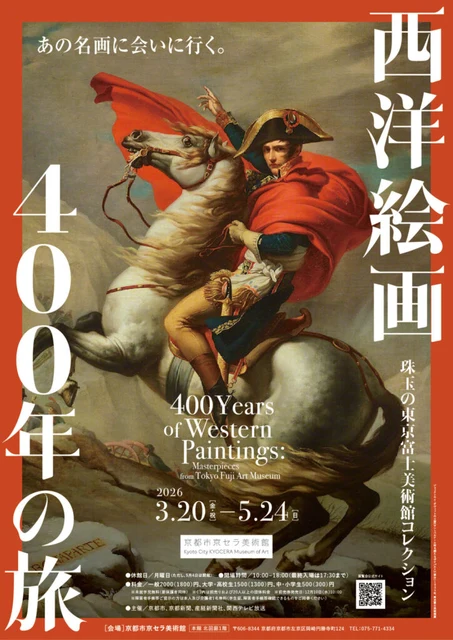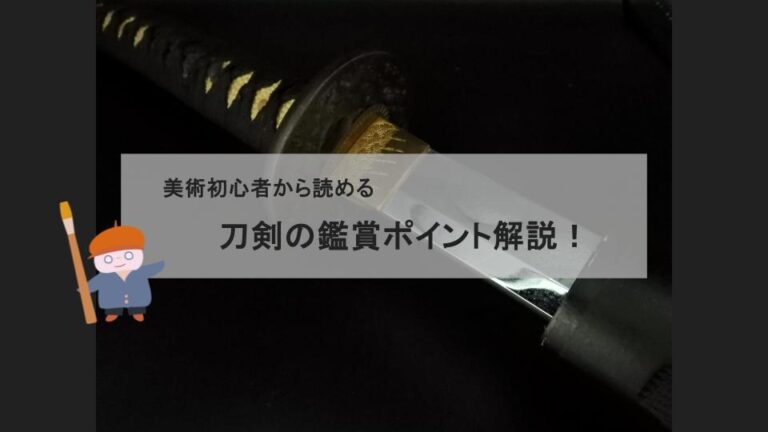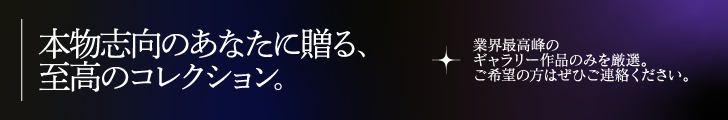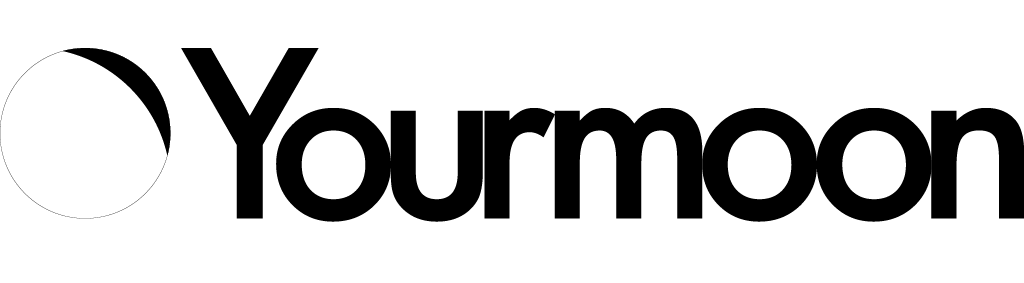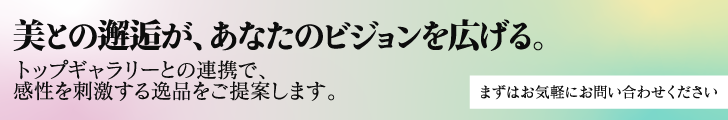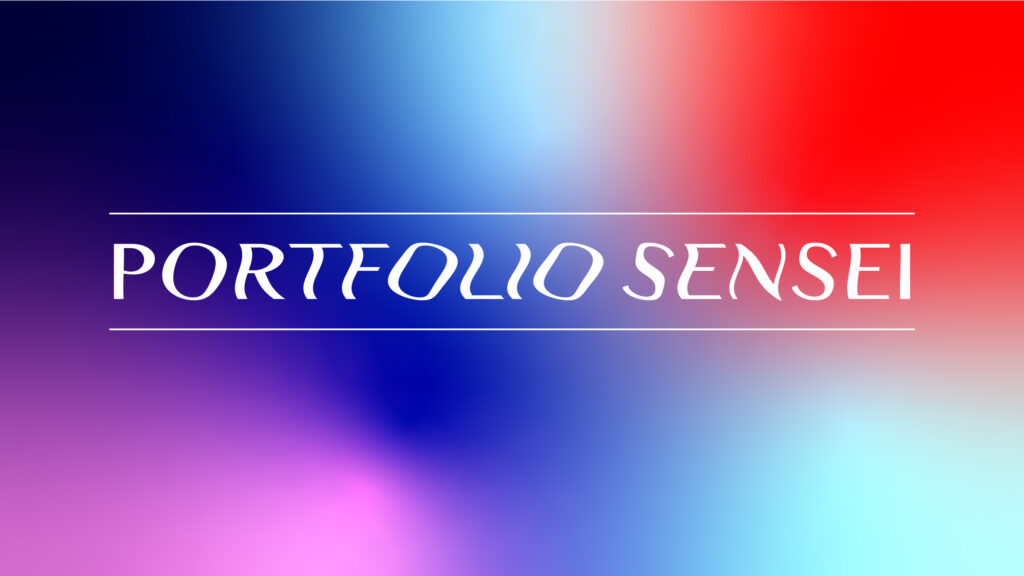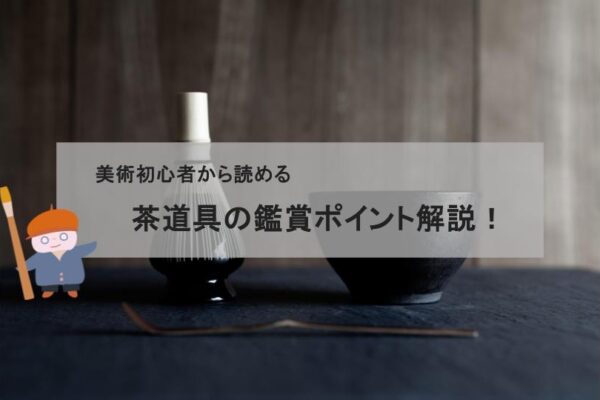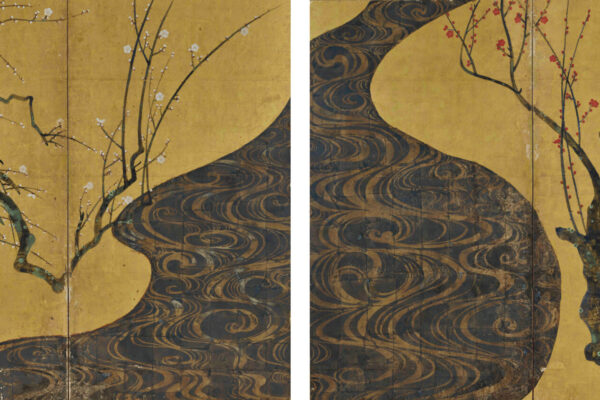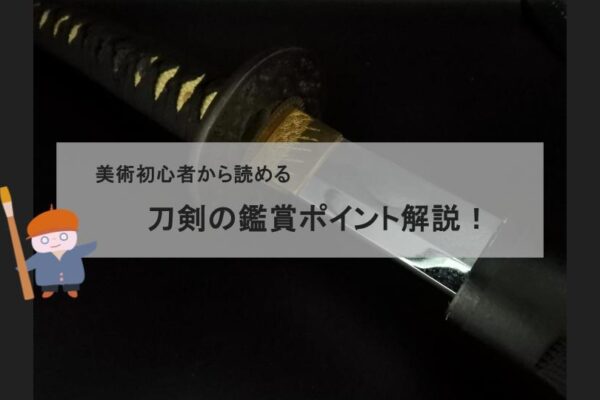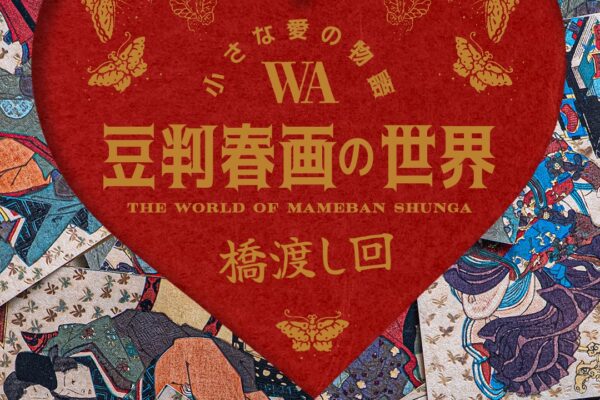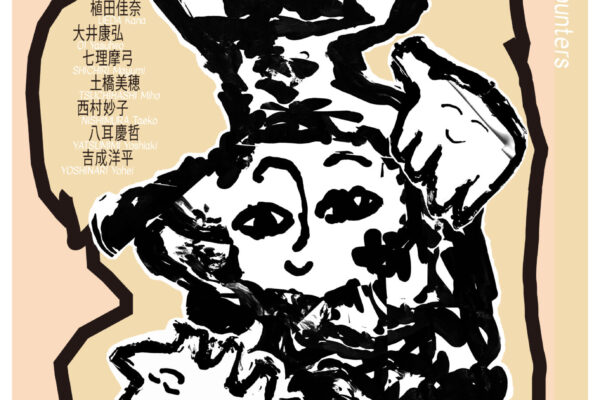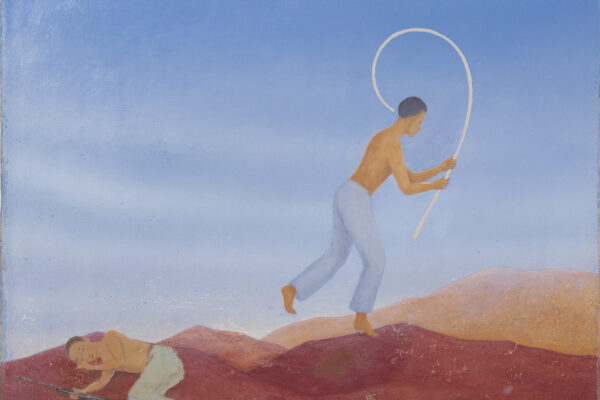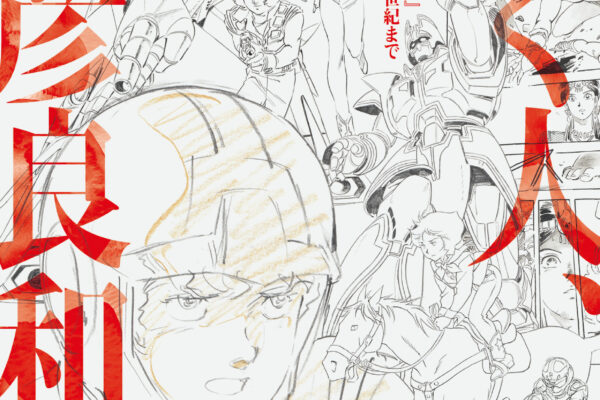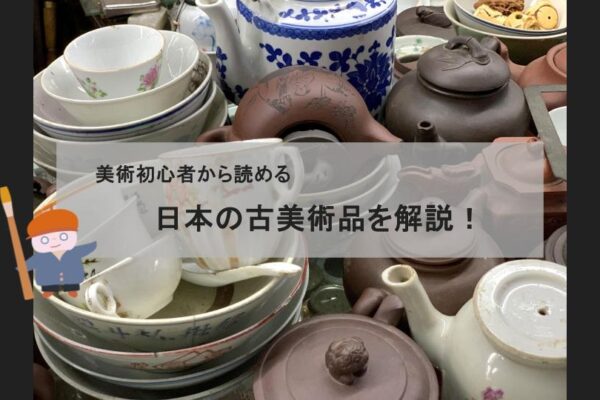こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。
皆さんはアートオークションをご存知ですか?
世界的なオークションハウスにサザビーズやクリスティーズが知られています。
外国の富裕層がピカソやバンクシーなどの有名な画家の作品をとんでもない金額で落札する、といったような華やかな世界というイメージがある方が多いのではないでしょうか。
それもアートオークションのひとつの側面です。
しかし、アートオークション自体は日本国内でも行われており、学生の作品だけを取り扱う小規模な競売もあります。
では、この二つのアートオークションの違いは何によって生まれているのでしょうか。
アートオークションの仕組みはどのように生まれたのでしょうか。
本記事ではそんなアートオークションの世界についてご紹介します。
コンテンツ
Toggle基本情報
アートオークションって?
アートオークションについて簡単に説明します。
アートに限らず金融市場やオークションにはプライマリ市場とセカンダリ市場の二つがあります。
プライマリ市場(第一市場)とは、画廊や百貨店が企画した展覧会に作家が作品を出品し、画商やコレクターが買い付けを行う場所です。現存作家が作品を世に出す場所はほとんどの場合がプライマリ市場になります。
作家が値付けをするにしろ、交渉を行って決めるにしろ、基本的には作家と購入者が一対一で売買契約を行います。
セカンダリ市場(第二市場)とは、画商やコレクターといった購入者の所有する作品がオークション会社を介して別の購入者の元に転売される場所です。
購入者が金額を提示するオークション形式で行われ、市場の潮流によってお金の流れが流動的に変わります。ある作家の作品が高額取引されたことで別の作品の価値が上がるなど、取引自体が市場価値に影響を与えるという点がセカンダリ市場の面白いところでもあり、難しいところでもあります。
セカンダリ市場に作家本人は介入しないのが常識でしたが、2008年に現代アーティストのダミアン・ハースト本人が自身の作品をサザビーズに出品するという事件が起こりました。
「Beautiful Inside My Head Forever」と称された2日間にわたるオークションは、合計落札金額1.1億ポンドを記録し、1人の芸術家の作品落札総額として当時の最高記録を樹立しました。
これ以降、作家が直接オークションに出品するケースが増えてきており、プライマリ市場とセカンダリ市場の境界は曖昧になってきています。
アートオークションの歴史とアートの価値
アートオークションの誕生
美術品が取引され始めた時代はいつ頃でしょうか。
明確には分かっていませんが、ローマ帝国には既に美術品を取引によって蒐集するコレクターが存在しており、古代ローマの詩人ホラティウスによると彼らが後に画商へと転じていったといいます。
この時代のアートの価値について、古代ローマの歴史家プリニウスがいくつかの記述を残しています。
それによると、美術家の作風と評判、または作品の主題が売れ行きの要因だと分析されています。
まず作家の評価が分析に挙げられている点は非常に興味深いです。現代でも作家のネームバリューは価値を決める大きな要因となっており「どのような作品か」よりも「誰の作品か」という評価方法は、アートに詳しくない人にもわかりやすいという良い効果があります。
主題についても、神々の姿や戦闘の勝利といった壮大な性格を持つ伝統的な場面を描いたものよりも、日常生活の情景を描いた絵に対する需要がローマ帝国では高まっているという興味深い記述も残されています。
さらに、売り手と買い手の価値観を上手く擦り合わせることができなかった時には、作品の「重量」で値段がつけられたとも述べられています。
美術市場の確立
西洋美術史で大きな潮流を生み出したルネサンス時代(十五世紀頃)、アートオークションの歴史にも動きがありました。
キリスト教の台頭により、宗教画や教会美術の価値が高まっていました。教会が巨大なパトロンとなり、作家に直接注文がされるようになりました。
ただし、この時代に宗教画ばかりが描かれていたというわけではなく、同時期に神話のシーンや肖像画、風景画といった主題も登場しました。
これらの作品は教会の援助を受けられず、直接受注もできないため、市場にだされることになります。
決められた日に露天商が集まり、売り買いが行われる最初の美術市場はヨーロッパの通商の大きな中心地だったフランドル(現在のベルギー周辺)に登場しました。
この時期、多くの流通に生産と通商の統制をはかる同業組合(いわゆるギルド)や通商会社が生まれており、美術市場にも例えば「ブルッヘ絵画制作者組合」という団体が登場しました。
彼らは売買期間を定めたり、監査人が品質の承認を行っていました。
この制度は現代でも行われる品質管理(クオリティ・コントロール)の祖先とも言える存在で、裏を返すとこれ以前の取引は買い手の目利きに委ねられていたとも言えます。第三者による審査制度が設けられたことでアートという曖昧なものにひとつの価値基準が生まれた瞬間かもしれません。
十七世紀に入るとルネサンス時代の巨匠の作品(ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ミケランジェロ、ティッツァーノなど)は、例えばジョルジョ・ヴァザーリのような美術史家、評論家などが伝記を残したことで「見えない価値」が徐々に高まっていきました。
また、教会が宗教美術を推奨していたことでアートは贅沢品や娯楽ではなくリベラルアーツへと押し上げられていきました。
ただしこれらの評判は必ずしも公正なものとは限りませんでした。
これは画商やコレクターと、美術史家や評論家が協力して特定の画家を好評したり、あるいは貶めたりすることがしばしばあったからです。
例えば、フランドルの巨匠ピーテル・パウル・ルーベンスの絵をフランスのリシュリュー公爵に大量に売った画商ジャン=ミシェル・ピカールという人物がいます。
彼がルーベンスの絵を売った1660〜1670年代と同時期に、美術史家のロジェ・ド・ピールが著作の中でルーベンスを評価し、フランスの画家ニコラ・プッサンよりも優れていると断言していたのは、まったくの偶然ではないでしょう。
不穏なことに、市場が活発になる「著名な画家」や「有力なコレクター」の死亡をいち早く聞きつけて売却の準備をする者や、作品を高く売るために事実とは異なる情報で価値を高めようとしたり、顧客のコレクションにケチをつける者もいたようです。
さらに露悪的なことを言えば、アーティストという生き物に付き纏う自殺や早世といった出来事を、肯定的に捉える慣習すら買い手にはあったかもしれません。
アーティストの作品価格にとって、自殺や早世が有利に働くことにはほとんど疑いがない。それはロマンチックなかたちの悲劇であり、また同時に、市場に出回る作品数を減らすことでもある。それに、彼らが老齢まで生きていたとしたら、おそらくはより劣った作品を生み出していたかもしれない。そうした良くない作品を供給することを差し止めるという意味でも、自殺や早世は市場にとって有利だからである。
(『サザビーズで朝食を 競売人が明かす美とお金の物語』P133-134から抜粋)
アートの価値が高まったことで、倫理に悖る方法で市場に取り入る者が現れたという構図は、我々も覚えがあるのではないでしょうか。
アートオークションの現在
冒頭に登場したサザビーズとクリスティーズは、現在のアートオークションを支配している二大巨頭といって差し支えないでしょう。
現在も操業する最古の国際競売会社であるサザビーズは、1744年3月11日のロンドンでジョン・スタンリー卿の図書館に所蔵されていた書籍を売却するために設立されました。サザビーズの名称は創業したサミュエル・ベイカーの甥ジョン・サザビーに由来します。
その22年後の1766年、同じくロンドンにジェームズ・クリスティーによりクリスティーズが設立されました。十八世紀末にフランス革命で命を落としたデュ・バリー夫人の宝石類の売却を手がけたことを皮切りに、英国の富裕層のコレクションを次々と売り立てて成長を遂げていきました。
十八世紀から第二次世界大戦後までアートオークションの市場を支配していたのはクリスティーズでした。サザビーズはその沿革から主に書籍類を取り扱っており、希少なコレクションが市場に出てきた時もクリスティーズと張り合うような経験も評判も持っていませんでした。
しかし十九世紀以降、伝統的な美を重視し豪華さや近代性の価値を認めない保守的なクリスティーズに対して営利的に貪欲だったサザビーズは徐々に成長。1917年のオフィス移転をきっかけに絵画や装飾品の競売に力を入れ始め1950年頃からアートオークションの道を先導するようになりました。
クリスティーズがどれくらい保守的(あるいは排斥的)だったかというエピソードに、旧英国領(オーストラリア、南アフリカ、カナダ等)出身のアーティストの作品はいっしょくたにされて「植民地セール」と呼ばれるカテゴリーに入れられていました。
現在のクリスティーズはむしろアート競売の最先端を行く、革新的な性質に変わってきているように感じられます。
現代アートの競売に力を入れ、2022年の現存するアーティストのオークション落札価格トップ3は、全てクリスティーズに出品された作品が占めています。
またオークションの約半数をオンラインで行い、NFTアートを初めて競売にかけたのもクリスティーズです。
一方、サザビーズはイギリスからアメリカに初のオークションハウスを設立し、初めてアジアでオークションを開催するなど市場拡大に力を入れるような成長が見て取れます。
初めて存命の現代アーティストの作品をオークションにかけたのもサザビーズで、クリスティーズに負けず劣らずの革新体制です。
国際的なアートオークションハウスと言えばこの二社で揺るぎがないと思いますが、近年では時計やジュエリーの競売を行っていたフィリップスが現代アートのオークションに参入し、第三のオークションハウスとして浸透し始めています。
最も高いアート
アートオークションが定める価値のひとつ、金額について見ていきましょう。
2025年2月時点での落札金額ランキングは以下の通りになっています。
順位 アーティスト 作品名 取引年 金額 1 ダ・ヴィンチ 『サルバドール・ムンディ』 2017年 約4億5000万ドル 2 デ・クーニング 『インターチェンジ』 2015年 約3億ドル 3 ポール・セザンヌ 『カード遊びをする人々』 2011年 約2億5000万ドル 4 ゴーギャン 『いつ結婚するの?』 2014年 約2億1000万ドル 5 ポロック 『Number 17A』 2015年 約2億ドル 6 アンディ・ウォーホル 『ショット・オレンジ・マリリン』 2017年 約2億ドル 7 レンブラント 『旗手』 2022年 約1億9800万ドル 8
アンディ・ウォーホル 『ショット・セージブルー・マリリン』 2022年 1億9500万ドル 9 ロスコ 『No.6』 2014年 約1億8600万ドル
10 クリムト 『水蛇Ⅱ』 2013年 約1億8400万ドル 11 レンブラント 『マールテン・ソールマンスとオーペン・コーピットの肖像』(2枚1組) 2015年 約1億8000万ドル 12 ピカソ 『アルジェの女たち(バージョンO)』 2015年 約1億7900万ドル 13 モディリアーニ 『横たわる裸婦』 2015年 約1億7000万ドル 14 リキテンスタイン 『マスターピース』 2017年 約1億6500万ドル 15 モディリアーニ 『(左向きに)横たわる裸婦』 2018年 約1億5720万ドル 16 ピカソ 『夢』 2013年 1億5500万ドル 17 クリムト 『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像Ⅱ』 2016年 約1億5000万ドル 18 スーラ 『ポーズ集、アンサンブル(プチ版)』 2022年 1億4924万ドル 19 ベーコン 『ルシアン・フロイドの3つの習作』 2013年 約1億4240万ドル
20 斉白石(チー・バイシ) 『山水十二屏』 2017年 1億4100万ドル 21 ポロック 『Number 5, 1948』 2006年 1億4000万ドル 22 ピカソ 『腕時計の女』 2023年 1億3900万ドル 23 セザンヌ 『サント・ヴィクトワール山』 2022年 1億3800万ドル 24 デ・クーニング 『ウーマンⅢ』 2006年 1億3700万ドル 25 クリムト 『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 I』 2006年 1億3500万ドル (「翠波画廊」ホームページより作成)
これまで最も高額で落札された芸術作品はレオナルド・ダ・ヴィンチの『サルバドール・ムンディ(1499-1510)』とされています。クリスティーズのオークションで、その金額はなんと約4億5000万ドル(約510億円)。
最も著名な絵画、そして最も高価な絵画として知られる『モナ・リザ』もダ・ヴィンチの作品です。
『モナ・リザ』は1972年12月14日の査定で1億ドルという評価がなされ、ルーヴル美術館は安全を期して同額の保険料を支払うことを決めたことで、最も高額な保険がかけられた絵画作品としてギネス世界記録に認定されています。
ダ・ヴィンチの美術史における功績は数多くありますが、膨大なスケッチを残した反面、完成した作品が少なく、絵を売った実績が少なかったため希少性が高いという側面があります。
また、アートオークションにはバンクシーのイメージがある方も多いのではないでしょうか。
2018年、バンクシー作『風船を持った少女(2004)』がサザビーズのオークションで約104万ポンド(約1億5000万円)で落札されたのと同時に額縁のシュレッダーが作動し絵画の下半分を切り裂くというアクシデントが起こりました。
後にYouTubeチャンネル「banksyfilm」で額縁の仕組みやリハーサルの様子が公開され、一連の騒動がバンクシーのパフォーマンスであったことが明らかになります。
アートが投機の対象として消費されていくオークション・ビジネスに一石を投じる目的が伺えるものでした。
しかしパフォーマンスの意図とは裏腹に、“アートオークションへのテロ行為”や“史上初、オークション中に生で制作されたアート”と大々的な話題となり、題名を『愛はごみ箱の中に』と改題して1858万ポンド(約28億8000万円)で落札されました。金額は裁断前の約18倍に及び、バンクシーのオークションレコードを記録しました。
このようなアクシデントが、作品に“箔”をつけることもあるのです。
日本人作家はアートオークションのランキングには載っていませんが、現代アーティスト売り上げランキングを見てみましょう。
順位 アーティスト 売り上げ高
1 ジャン=ミシェル・バスキア 約2億3500万ドル ($235,524,904) 2 奈良美智 約9000万ドル ($97,737,808) 3 バンクシー 約4800万ドル ($48,873,898) 4 セシリー・ブラウン 約4700万ドル ($47,713,568) 5 ジェフ・クーンズ 約3600万ドル ($36,136,551) 6 キース・ヘリング 約3500万ドル ($35,807,795) 7 クリストファー・ウール 約3300万ドル ($33,671,700) 8 ダミアン・ハースト 約3200万ドル ($32,722,142) 9 ジョージ・コンド 約3200万ドル ($32,064,762) 10 マーク・グロッチャン 約3000万ドル ($30,025,287) (『THE 2023 CONTEMPORARY ART MARKET REPORT』より作成)
1位のバスキアは、27歳の若さでこの世を去ったため現代アートにカテゴリされながら新作が望めない、つまり出品される作品数が限られています。
2位の奈良美智作『Knife Behind Back(2000)』は2019年にサザビーズのオークションで約2500万ドル(約27億円)で落札されました。これは存命作家最高落札価格を記録しています。
アートの価値を決める要因の一つに希少性があります。新作の望めないこの世を去ったアーティストの作品は、高額になる傾向にあります。
また、かつてジョルジョ・ヴァザーリがそうしたように評論家によって作家の権威が“神話”として喧伝されることで価値が高騰するという要因もあります。
そのため存命の作者が多い現代アートはランキングやレコードに載る規模にはなりにくいのですが、中でもバンクシーと奈良美智は目を見張るものがありますね。
まとめ
いかがだったでしょうか。
アートの価値は人それぞれという部分は間違いなく、それ故にアートの面白さや魅力は分かりづらいという側面があるかと思います。
特に抽象絵画や現代アートといった文脈のあるジャンルはことさらに、その面白さを伝えることにカロリーを必要とします。SNSで「これの何が面白いの?」といった意見を見かけてモヤモヤしているのは私だけではないのではないでしょうか。
そんな時、ひとつの指標になるのが金額だと思います。
パッと見の印象からは思いがけない金額が動いている事実を知ることで「どうしてこんなお金が動いているんだろう」という理解のステップに進むことができるのではないでしょうか。
今回はそんな思いで、芸術とお金、そしてそれを動かすアートオークションの世界について解説しました。
おすすめ書籍
アートオークションをもっと知りたい方にはこちらの書籍がおすすめです!
『華麗なる美術オークションの世界 クリスティーズの内訳』
クリスティーズが十九世紀に迎えた経営危機を主題に、当時のアートオークションを取り巻く歴史と共にどのように現在の状況へと成長していったのかが書かれた書籍です。著者のジャーナリストはクリスティーズのみならずサザビーズへの綿密な取材も通して、まるで自伝的な本に仕上がっています。かなりハイカロリーな本ですが、邦訳本の中で最もクリスティーズの沿革に詳しい本だと思うので興味のある方はぜひ手に取ってみてください。
『ならず者たちのギャラリー 誰が「名画」をつくりだしたのか?』
著者はサザビーズの取締役を務める競売人フィリップ・フック。アートオークションのトップ人物が、アートオークションの歴史から、アートの価値をどのように先導してきたのかが綿密に書かれています。たくさんの事例が紹介されているので、これを読み通せばアートオークションの歴史が外観できると思います。
『サザビーズで朝食を 競売人が明かす美とお金の物語』
こちらもフィリップ・フックによる著作で、内容はアートオークションの仕組みそのものというよりは、作家やジャンルごとにどのような価値が見出されてきたのかが解説されている本です。興味のあるトピックから読み進めることができるので、読みやすく「アートの価値」について知見を得られる本です。
『巨大化する現代アートビジネス』
アート市場が持つビジネス的な側面についてジャーナリストの著者が取材を行った書籍。作家、画商、ギャラリー、オークショニスト、顧客が入り乱れるマネーゲームについて生々しい取材内容が書かれています。アートオークションの仕組みから、一歩先に踏み込んだプレイヤーの思惑を知りたい人におすすめの一冊です。