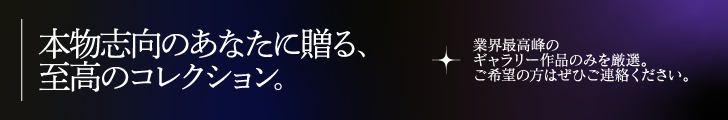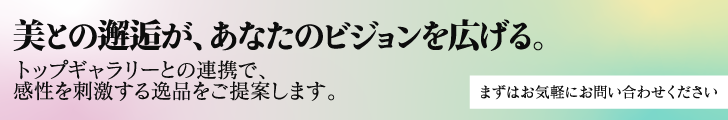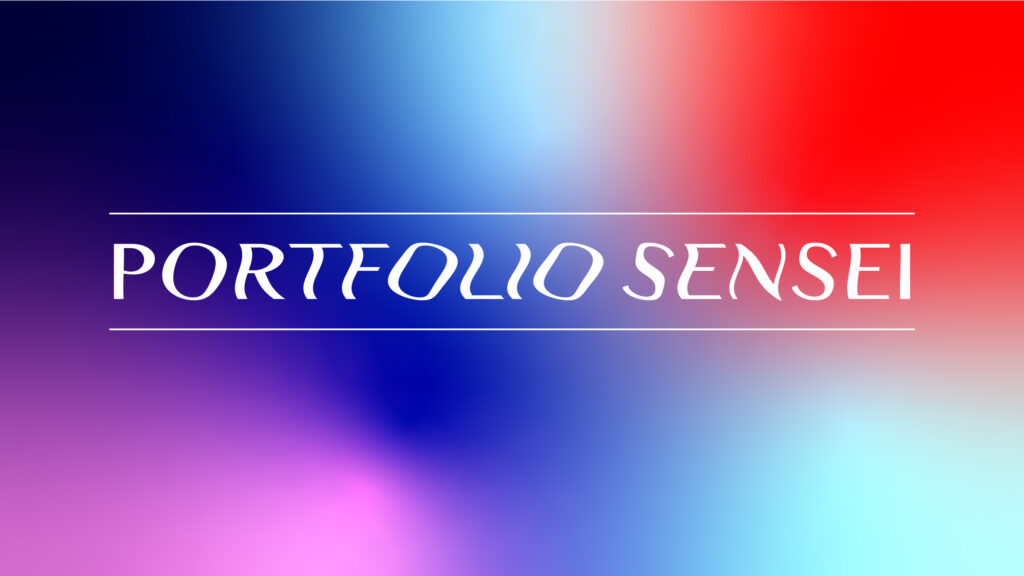こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。
皆さんはルイーズ・ブルジョワという人物をご存知ですか?
ルイーズ・ブルジョワはフランスに生まれ、アメリカを中心に活躍した女性アーティストです。
六本木の森美術館にある『ママン』はトレードマーク的な存在になっており、見たことがある方も多いのではないでしょうか。
不気味にも感じる彫刻ですが『ママン』をはじめルイーズの作品は、彼女が人生で経験した女性の手仕事や母親像などが込められた奥深いものがたくさんあります。
本記事ではルイーズ・ブルジョワの人生と作品についてご紹介します。
コンテンツ
Toggleルイーズ・ブルジョワって?

基本情報
| 本名 | ルイーズ・ブルジョワ(Louise Bourgeois) |
| 生年月日 | 1911年12月25日~2010年5月31日(98歳没) |
| 国籍/出身 | アメリカ合衆国/フランス パリ |
| 学歴 | エコール・デ・ボザール、ルーブル学院他 |
| 分野 | 絵画、彫刻、インスタレーション |
| 傾向 | 現代彫刻、インスタレーションアート |
| 師事した人 | フェルナン・レジェ他 |
経歴と作品
生まれと環境
1911年12月25日、フランスのパリ郊外の家庭でルイーズは生まれました。
ルイーズの家庭は祖父母の代からタペストリーの修繕を行う工場を営んでおり、幼い頃から両親が手仕事で家庭を支えているのを見て育ちます。
父ルイは工場を継ぐ男児が生まれてくるのを期待していましたが、長女であるルイーズの姉に続いて女児が生まれたことに失望を口にしていました。
そのプレッシャーを一心に受けていた母ジョセフィーヌは、タペストリー工場を立ち上げた父にただ献身的な妻ではなく、女性マネージャーとしてもルイを支えていました。
後継を産まなければならないというプレッシャーからノイローゼを患う母。
食事をするだけの“無駄口”とルイーズを罵りながらも、たしかに工場経営で家族を養う父。
そんな両親を見ていたルイーズは、幼い頃から絵に関心を持ちながら、いつか父に認められたいという願望を持っていました。
母の役に立ちたくて、父に認められたくて
10歳になったルイーズは、楽しそうに絵を描く様子を見た母からタペストリーの柄の下絵を描いてみないかと頼まれます。
生まれてきた意味を責める父と、働けない娘たちに代わって仕事をする母を見て育ってきたルイーズにとって、これは願ってもない提案でした。
仕事を任されてすぐに頭角を現しはじめたルイーズはしばしば下絵を褒められ、たしかに家の役に立っているのだと実感するに至ります。
それは父からのいじめへの反抗心と、母への罪悪感が生み出したアクションと言えるものでした。
父は工場を経営する優秀な人物でしたが、後継が生まれないという不安と、経営者でありながら徴兵に行かざるを得ない身分が重なりしょっちゅう癇癪を起こしていました。
ルイーズはその捌け口としてたびたび父からいじめやセクハラを受けながらも、反抗せず、なんとか手仕事で家庭に貢献することで耐えていました。
母が第三子にようやく男児を産んだことで父からのハラスメントは一旦おさまりますが、すでに父の存在に依存していた母はたびたびヒステリーを起こすほど精神が不安定な状態でした。
奇しくも、家庭環境からのプレッシャーがルイーズを手仕事に巡り合わせたのでした。
女性の存在意義と、父からの手のひら返し
ルイーズが11歳の頃、家庭教師として雇われた18歳の女性サディが家にやってきます。
立て付けとしては家庭教師でしたが、父ルイの愛人であったことは振る舞いから明らかでした。
妻子のいる前でサディに愛情を注ぎ、あまつさえ母をベッドから追い出してサディを迎える父の横暴を思春期のルイーズは目の当たりにしたのです。
この頃の家庭環境は、ルイーズの女性像に大きな影響を与えたことは間違いありません。
しかしルイーズは「成功しようがしまいが、恐れる必要はないわ。おまえに必要なのは、他の誰にも代われない必要不可欠な存在になることよ」という母の言葉を信じ、変わらず両親に認められるために勉強や仕事に向き合い続けました。
その後、ルイーズは私立学校を卒業し、名門であるソルボンヌ大学に入学します。
すると、父の態度は急変します。
大学入学というわかりやすい結果を示すことができたルイーズを、手のひらを返したように甘やかすようになったのです。
このことにルイーズは、やっと親に認められたという安心感を覚えた一方、自分自身の存在意義についての悩みもまた芽生え始めました。
母の死と、作家としてのスタート
父からの仕送りを受けながらルイーズは、大学で数学や天文学などの学問を学び始めます。
しかし、在学中に母が亡くなってしまいます。
ショックを受けたルイーズは、大学を卒業後、タペストリー工場の仕事に戻ります。
ルイーズの心を癒したのは、アメリカで発達した前衛芸術・抽象芸術といった自由な気風のアートシーンでした。
のびのびとした表現方法に感銘を受けたルイーズは、美術の道に生きがいを見出そうとします。
いくつかの美術学校を経て、ルーブル美術館のガイド係のバイトをすることで受けられる学費免除を頼りにルーブル学院への入学を果たします。
学業もさることながら、美術館のバイトや画家のアトリエを訪ねた経験を生かして、自身もひとりのアーティストとして制作を始めました。
しかしこの頃、父からの仕送りが途絶えます。
当時の価値観では、女流作家の立場は低く、アートシーンはほとんど男性の独壇場でした。
つまり当時の女性アーティストは将来性がなく、父は作家としてのルイーズに期待が持てなかったということでしょう。
母の死に続いて、父や画壇の男性から見て取れる格差に、ルイーズは絶望とも言える衝撃を受けます。
作家としてのスタートラインに立ったルイーズは、これまでの経験に「女性の存在意義」が通底していることに改めて気づいたのです。
自由の国アメリカでの出会い
『Femme Maison(1945-7)』

ルイーズ・ブルジョワを代表する作品のひとつに、この『Femme Maison』シリーズがあります。
Femme Maison(ファムメゾン)はフランス語で「女性の家」を意味し、そのタイトル通り裸の女性の体が建物と融合したような図像が描かれています。
父の経営に従事する母や、アーティストとしての将来性を見限られた自身の経験から、女性のアイデンティティが家庭に置き去りにされているという問題提起をした作品です。
現在はデリケートかつセンセーショナルな問題ですが、フェミニズムという考え方も当時はまだ注目されていなかった時代にあって前衛的な作品でした。
当時、第二次世界大戦の混乱でフランスはアメリカに移住する人が多くおり、ルイーズらも例外ではありませんでした。
フランスでは、父がタペストリーを展示するギャラリーの横で絵画の展示をしていたルイーズでしたが、1938年、アメリカ人美術史家のロバート・ゴールドウォーターと仕事を通じて仲を深め結婚に至ります。
その後、養子を含め三人の子供をもうけ、家庭を築いたルイーズはニューヨークに移住します。
移住後は自身の制作も精力的に行いはじめ、ゴミ捨て場の廃棄物や流木を用い、幼少期に感じた捨てられることへの恐怖を表現した作品群を制作しました。
1945年にペギー・グッゲンハイムの『Art of This Century』 で、14名の女性アーティストの作品を集めた『The Women』への出品でもってアーティストデビューを果たします。
当時、女流アーティストの立場は低い上、現在ルイーズの作品を評するのに用いられるフェミニズム・アートという言葉も一般的ではありませんでした。
そのためルイーズの作品は当時はあまり注目を浴びず、大々的な評価を受けるのには時間がかかりました。
61年の時を経ての再評価
『Femme Maison(1982)』

『Femme Maison』シリーズは時代と共に絵画だけではなく、彫刻作品としてのバリエーションも生まれました。
この作品では粘土とマネキンの手足、髪の毛を使って、よりリアルに女性のアイデンティティの姿をわたしたちに認識させるようになっています。
この後、ルイーズは細々と制作を続けますが高い評価を受けることはしばらくありませんでした。
生活を支えるために織物仕事をしていたルイーズは、1943年、32歳の時にルイーズは作り溜めたタペストリーの作品を展示します。
さらに6年後、初めての彫刻作品の展示が行われました。
1951年に父が亡くなり、実家のタペストリー工場が閉鎖されることになります。工場を畳んだルイーズは、ブルックリンの衣料品工場を買い取ってアトリエとしました。
この頃の父への思いは詳細に明かされてはいませんが、ルイーズは1948年に父をニューヨークの住まいに招いています。
その上で、父の遺産とも言える工場を(形は違えど)受け継いだルイーズには、幼少期に受けた父の所業を超克する思いがあったのではないでしょうか。
決して恵まれた家庭環境ではなかったかもしれませんが、父の工場と母の手仕事がルイーズをアーティストにし、存在意義を与えたのは間違いないでしょう。
このような複雑な家庭環境に決着がつき、細々とした制作の日々に戻ったルイーズ。
画壇の風潮にも変化が起きた1982年、ルイーズが72歳の時にニューヨーク近代美術館で個展が開かれました。
この個展でルイーズの作品は注目を浴び、過去の作品も含めて再評価されることになります。
制作を始めた当時では注目されなかった女性アーティストという立場や、フェミニズム・アートというジャンルが大きな話題を呼び、ルイーズはフェミニズム・アートのシンボル的存在に駆け上がっていきます。
ルイーズの存在がフェミニズム・アートの先駆けとなり、ジュディ・シカゴやバーバラ・クルーガーといった女性アーティストが時代を前後して活躍し始めます。
超克の彫刻 『ママン』の制作
『Maman(1999)』

おかあさんの姿は すこしもクモには 似ていなかったけど
こわれたものを なおすところが 同じだったからです
「クモは 巣をこわされても おこらない もういちど 糸をはきなおすだけ」
{出典:Coxon,Ann. Louise Bourgeois. London:Tate Publishing.2010(Louise Bourgeois Taped Inter-view with Cecilia Blomberg. 1968).}
1990年代からルイーズは、クモをモチーフとした彫刻作品を制作します。
元々は1947年のスケッチを原案、1996年に制作された『Spider』を習作として、1999年にルイーズが「The Unilever Series」の年次委員会就任に際して『Maman』が制作されます。
『Maman(ママン)』はルイーズの母国フランスで「母」を意味し、ルイーズの母ジョセフィーヌの織物仕事、家事や育児の様子、母親という存在の強さがクモというモチーフに表れています。
ルイーズにとって家族の思い出は、決して楽しいことだけでも辛いことだけでもありませんでした。その経験は生涯を通して母性や女性性について向き合うことになるアーティスト性を育てていくことになります。
ルイーズの人生において『Maman』に代表される彫刻作品は、実はそれほど多くなく、父の死後にアトリエを構えた1960年から1990年頃に集約されています。
『Maman』のようなオブジェサイズの作品は初めてといってもよく、巨大でリアルな彫刻でもって生家の思い出を清算するような思いがあったのかもしれません。
晩年
再評価を受けてルイーズは女性アーティストのシンボル的な立ち位置を確立し、1993年のヴェネツィア・ビエンナーレではアメリカ館で展示が行われ、ドキュメンタリー映画が制作されるに至ります。
これまでの人生にあった苦難を清算するかのような栄誉に囲まれる中、2010年5月31日に心臓発作でこの世を去ります。
ルイーズは98歳で亡くなるまで生涯現役で作品を作り続けました。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
現代では画壇の風潮も大きく変わり、女性アーティストならではの表現方法に注目が集まるような機運があります。
その背景には、ルイーズ・ブルジョワをはじめとする多くの女性アーティストの存在が欠かせませんでした。
その中でも、女性アーティストの存在が受け入れられるまでの長い時代を生涯現役で横断したルイーズ・ブルジョワは記念碑的な存在だと言えるでしょう。
おすすめ書籍
ルイーズ・ブルジョワについての知識を深めたい方はこちらの書籍もおすすめです!
ルイーズ・ブルジョワ 糸とクモの彫刻家
ルイーズに関する書籍は数少ないですが、その中の一つがこの書籍です。こども向けに書かれた絵本調の書籍で、ざっくりとですがルイーズの人生と、糸とクモというモチーフを中心に内面的な部分を描いています。