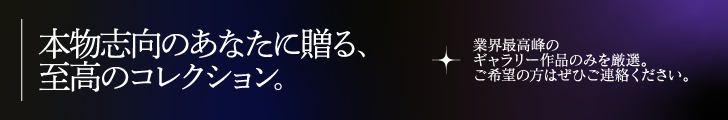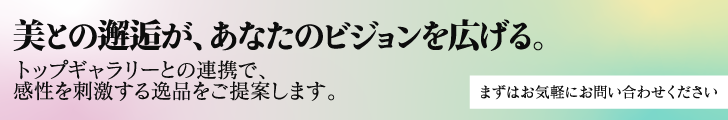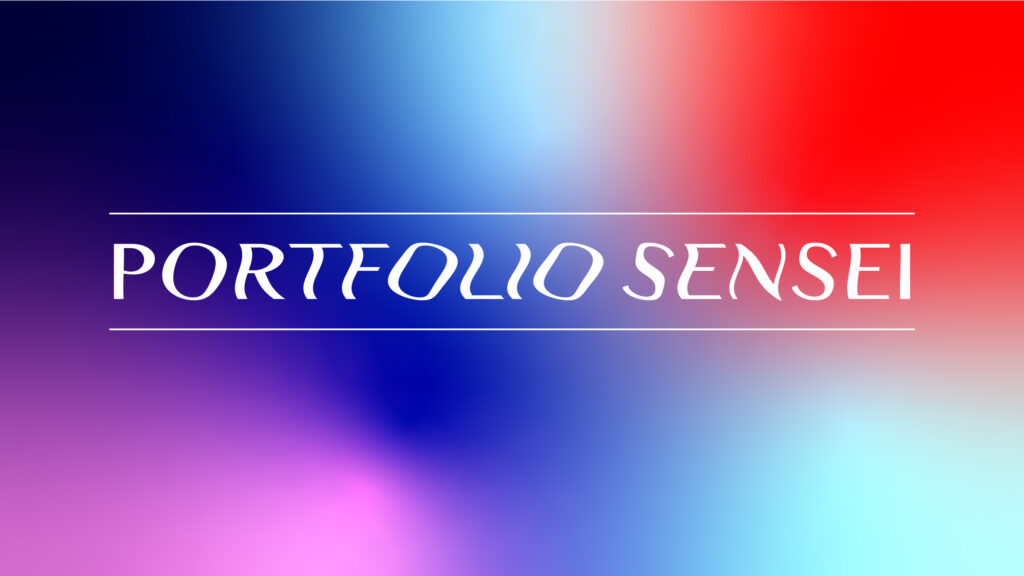こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。
皆さんはカミーユ・コローという画家をご存じですか?コローは19世紀フランスに生まれ活動した画家で、身近にある風景や友人の肖像などを描き、後に芸術運動として確立する印象派やモダニズムの橋渡しをした人物として知られています。
また、バルビゾンという村でミレーやルソーと共に風景画に取り組んだ『バルビゾン派』としても知られ、その中心人物である『バルビゾンの七星』にも数えられています。
本記事ではそんなコローの生涯と作品についてご紹介します。
コンテンツ
Toggleカミーユ・コローって?
基本情報
| 本名 | ジャン=バティスト・カミーユ・コロー(Jean-Baptiste Camille Corot) |
| 生年月日 | 1796年7月16日〜1875年2月22日(78歳) |
| 出身 | フランス |
| 分野 | 油絵 |
| 傾向 | アカデミズム絵画 バルビゾン派 |
| 師事した人 |
|
アカデミズム絵画って?
アカデミズム絵画とは、アカデミーの指導者に影響された画家たちを指す言葉です。
主には新古典主義とロマン主義運動の下で実践され、その統合を試みようとする動きのことを指すこともあります。
そのため「折衷主義」、「混合主義」とも言われます。
経歴と作品
コローの生まれと環境
コローは1796年、現在のフランス、パリ9区にある裕福な家に生まれました。
母は高級婦人帽屋を経営し、父はその会計係として働いていました。
共働きで忙しかったためか、コローは生まれてすぐ里子に出され、のちに家に戻って小学校に通い、中学校時代はノルマンディーの首都ルーアンに住むセヌゴン家に預けられます。
学業に才覚を見いだせなかったコローは中学を中退し、寄宿舎でかろうじて中学の過程を修めます。
一見、芸術と関わりのない環境に生まれ育ったコローですが、身なりの良い上流階級の人物が出入りする家に生まれたことや、中学時代を過ごしたセヌゴン家では、フランスの哲学者ジャン=ジャック・ルソーの自然主義に影響を受けたことはコローの美的感覚に大きく影響したと考えられます。
パリ市内で布地商に勤める傍ら、夜はデッサン・スクールに通い画家になる決意を固めていました。コローが通っていたアカデミー・シュイスはパリにある私立の画塾で、授業料が安く貧乏な画学生に人気の画塾でした。
ポール・セザンヌやカミーユ・ピサロ、アルマン・ギヨマンなどもこの画塾で学びました。
コローの画家への道は当初父に反対されていました。
しかし妹の病没によって与えられた年金が与えられたことで許しを得、26歳でようやくアトリエを建て画家への道をスタートさせます。
第三の風景画派
コローは同年代の友人であったアシール=エトナ・ミシャロンに風景画を学びますが、ミシャロンが23歳で急死したため、その後はミシャロンの師であったジャン=ヴィクトール・ベルタンを第二の師とします。
この頃のフランスでは風景画は2つの派閥に分かれていました。
第一のものはベルタンなどに代表される新古典主義的風景画派で、サロンや美術学校などでも認められた羽振りの良い派閥でした。
ありのままの風景ではなく絵的に美しい理想的な風景として再解釈したもので、純粋な風景画ではない代わりに絵画のジャンルにおいて歴史画と同じような高い地位にありました。
第二のものはルイ=ガブリエル・モローに見られるような伝統的な派閥で、戸外制作によってありのままを忠実に描くことに重きを置いていました。
実際の風景を時間を追いかけながら描くことでしか描けない光や空気の調子は作家の感受性がそのまま問われる制作方法で、その中でもリチャード=パークス・ボニントンの作品は、コローに大きな影響を与えたと考えられます。
コロー研究家のジェルマン・バザンによると、この頃、どの派閥にも属さない第3の風景画派が誕生しようとしていたようです。
その派閥は自然の力を恐れ、また陶酔するロマンティストたちで、ポール・ユエやテオドール・ルソーなどがその先達として活躍しはじめていました。
コローは師のベルタンの影響もあり第1の派閥である新古典主義的風景画に習っていましたが、その思想に大きく影響する出来事が1825年に訪れます。
イタリアでの革新
1825年、コローは3年のあいだイタリアへ滞在します。ローマ、ナポリ、ヴェネツィアなど自然豊かな都市を転々としたコローは、すっかり凝り固まっていた新古典主義を忘れ、純粋な感性によって風景を描き留めはじめます。
『ローマ、コンスタンティヌスのバシリカのアーケードから眺めたコロセウム(1825)』
第一回のイタリア滞在時に描いた、通称『バシリカのコロセウム』。伝統的な構図から脱却し、歴史的建造物であるコロセウムのある風景を豊かな光の解釈と自由な筆致で描いた本作には、現在で評価されているコローの技法のいくつかが見られるのです。
例えば、遠方に見えるコロセウムの壁面は細かく観察したような筆致ではなく、その量感を表現するようにどっしりとした色調で描かれています。
一見未完成にも見えるこの筆致は、ありのままの風景をカンヴァスに再現するだけでなく、見たものにコローが見た風景を想像させる余白のようなものを残しているのです。
イタリア到着時の手帳には「最初の一息でなされたものは全て形体もより自由でより美しく、また偶然の効果も大いに生かせることに私は気づいた。
これに反して、筆を重ねるときにはしばしば最初の色合いの調和を見失う」と書かれています。手を入れるほどに迷走する、表現者なら誰でも経験したことのあるジレンマに、あえて未完成で、イメージが自由に飛び回る余白を作るという形である意味での答えを出したのです。
『シャルトル大聖堂(1830)』
イタリアから帰ったコローは、フランス各地で制作を行い、イタリアで得た気づきを次々と形にしていきました。その中の傑作の一つが『シャルトル大聖堂』です。
大胆にまとめられた前景と描き込まれた大聖堂によって視覚的なコントラストを生み出しつつも、画面自体はひとつのブロンドのグラデーションによって表現されています。
この絵は40年以上も手許に置かれたのち、1872年にファンであったアルフレッド・ロボーに譲られ、左の人物が書き加えられました。
ここからさらにコローは、いくつかの風景を一つの画面に組み合わせた構成風景画に、聖書や古典の人物を登場させた、より高級なジャンルを開拓することを目指します。
ロマンティックな主題を求めて、シェイクスピアやゲーテ、ダンテなどの文学からも影響を受けています。この時期のコローは、長い時間をかけた自然の観察の中で、自然の美しさよりも感情的で、ノスタルジックな表現が価値を持ちはじめたようです。
『朝、ニンフの踊り(1850)』
その転機となる作品が『朝、ニンフの踊り』です。新古典主義的な神話・宗教の世界の代わりに、ロマン主義的な文学・舞台の主題を前面に押し出したことで儚い夢想世界や、ファンタジー的な世界観を表現したこの作品は、サロンに出品され、その挑戦的なテーマに対して高い評価を受けました。
明確な主題や風景の持つ固有な性格はもはや無意味となり、コローがロマンティックな印象を表現するために好んだ霧がかった朝、夕焼けといった風景は、その後の風景画に大きく影響しました。
1864年、精力的にサロンに出品し続けたことでコローはサロンの選考委員に任命されます。
『朝、ニンフの踊り』以降、サロンにも民衆にも評価を受けていたコローは、同じようにロマンティックな作品を多く描き残しています。
しかしそれは安易で感傷的なバリエーションに陥ってしまっている事を示していました。それは時に、コローの声価を傷つけることもあったようです。
『真珠の女(1868~1870)』
1866年になるとコローは痛風を患い、思うように戸外制作ができなくなっていました。
その影響か、晩年のコローの作品には一気に肖像画が増えます。ここでも、人物の個性や容貌に注目したものではなく、あくまでコローが思い描く詩的な世界観を表現するための、まさにモデルといった扱いでした。
実際、コローの死後の売り立てでも肖像画は押し並べて「猿たち(サンジュ)」と呼ばれて安く買われていったほどです。しかし注文を受けて描いたものではなかったことから、晩年のコローが自由な立場で行った実験的な作品という側面もあるでしょう。
その中でも有名なのは『真珠の女』でしょう。レオナルド・ダ・ヴィンチの描いた『モナ・リザ』のヴァリエーションとして描かれたこの作品は、木の葉の冠を抱いた女性が佇んでいて、コローの出発点である自然愛に立ち返ったような雰囲気を持っています。
しかし、『真珠の女』というタイトルからもわかる通り、額に落ちた葉の影が真珠の額飾りだと誤解され、批評の種ともなっていたようです。
『青い服の婦人(1874)』
コローの最晩年に描かれた肖像画である『青い服の婦人』は、コローの死後から25年経った1900年、パリ万国博覧会で初めて公開されました。
モデルはコローの他の絵でもたびたび描かれたエマ・ドービニーと考えられており、モデルの優美で記念碑的な佇まいと影のある表情が主題的なコントラストを、ブラウン調の室内と青い服による暖色と寒色の視覚的なコントラストが同時に描かれた、コローの肖像画の中でも有名で注目されている作品のひとつです。
純粋な風景画家
1875年2月22日、病のためにコローは死去します。生涯未婚であったコローは、その人生をひたすらに芸術に費やしたと言えるでしょう。
事実、コローは今でこそ十九世紀の西洋芸術を代表する風景画家として高い評価を受けていますが、生前は、近代における「呪われた芸術家」のような悲劇的なクライマックスも、新しい理論や人を驚かせる芸術上の変革もなく、サロンや社会との反抗、政治に翻弄されるようなエピソードとも無縁でした。
その上でコローは、まるで幼児のような純粋さで、ある時は自然、ある時はロマンティシズムと、自分が情熱を感じる対象をただひたすらに追いかけ、その情熱をカンヴァスにぶつけ続けたのです。表現者というよりも中世の職人のようなその気質は、制作においてコローの何よりの武器であったことでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
新古典主義から自然風景、ロマンティシズムなど、思いの向くままにテーマを柔軟に変えるコローの制作スタイルは、近代芸術に多く見られるサロンとの対立とは正反対のもので、著名な芸術家の人生に比べると波瀾万丈とは言えないものかもしれません。
しかし『真珠の女』の項で述べた通り、コローの中の主題や信念が十全に伝わらず、苦悩したこともあったようです。そのような苦悩があったからこそ、純粋に自らが感じたものを全力で表現しようと人生を芸術に捧げたとも言えるでしょう。
出典
坂本満著『新潮美術文庫本21 コロー』新潮社、1974年。